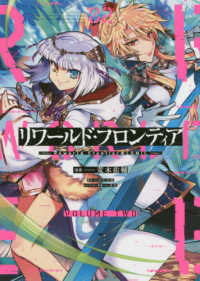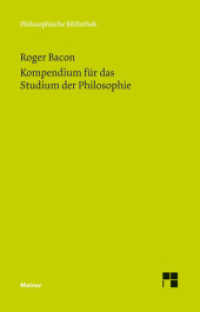内容説明
アメリカン・スクールの見学に訪れた日本人英語教師たちの不条理で滑稽な体験を通して、終戦後の日米関係を鋭利に諷刺する、芥川賞受賞の表題作のほか、若き兵士の揺れ動く心情を鮮烈に抉り取った文壇デビュー作『小銃』や、ユーモアと不安が共存する執拗なドタバタ劇『汽車の中』など全八編を収録。一見無造作な文体から底知れぬ闇を感じさせる、特異な魅力を放つ鬼才の初期作品集。
著者等紹介
小島信夫[コジマノブオ]
1915年、岐阜県生れ。東京大学英文学科卒。1954(昭和29)年「アメリカン・スクール」で芥川賞、’65年『抱擁家族』で谷崎潤一郎賞、’72年『私の作家評伝』で芸術選奨文部大臣賞、’81年『私の作家遍歴』で日本文学大賞、’82年『別れる理由』で野間文芸賞、’97(平成9)年『うるわしき日々』で読売文学賞。2006年遺作『残光』を発表後、肺炎のため死去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
遥かなる想い
243
第32回(1954年)芥川賞。 英語の教師達のアメリカンスクール見学を 通して、敗戦後の日本人の劣等感を執拗に 描く。 伊佐という教師の滑稽なほどの「英語」へ の畏れが面白い。 登場人物が 持つ「英語」への奇妙な拘りは 当時の日本人がアメリカに対して、 心に抱えていたものだったのだろうか? 「敗戦国」という 卑屈で 薄暗い 日本人の心象風景が 巧みに描かれた 短編だった。2017/06/27
ヴェネツィア
212
表題作の「アメリカン・スクール」は、第32回(1954年下半期)芥川賞受賞作。今読むと、驚くほどにその時代の空気を反映した作品だ。素材のあまりの時代錯誤に目を眩まされて、小説としての正当な評価が困難なほどだ。しかも、当時はそうではなかったのかもしれないが、今では登場人物たちの行動は、いずれも滑稽としか映らない。英語力を誇示しようとする山田、徹底して逃れようとする伊佐、中立的でありながら英語に堪能なミチ子。ここには強烈なまでのアメリカや英語に対するコンプレックスが吐露され、それはもはや爽快ですらある。2014/06/13
absinthe
173
表題作、戦後の混乱期の様子と、鬱屈した日米関係と感情。劣等感と優越感。どれもどこかねじくれている。靴擦れを気にしながらも車に乗らないへそ曲がりだが。英語の離せない英語教師という設定も面白く、場面が浮かびやすいのも特徴。『汽車の中』終戦期の混乱は凄かったのだ。満員電車などというものではなくどこか後進国を見ているよう。『小銃』『鬼』など他の作品も面白かった。人物や背景にそれぞれ何かを直接象徴させるのが好きらしい。一種の寓話。2021/10/05
翔亀
69
予想外の新鮮さ。早いもので昭和23年、終戦直後の作だ。作者は終戦時30歳で、出征しているから戦争体験が重い。『汽車の中』は、悲惨な超満員の東京への列車を描く。しかし車内のスシ詰め状態が、両手両足が空中で雁字搦めになって"浮遊"するSF的宇宙船のような非現実的な様相を示す。戦場生活では三六銃が「女の腕」となり(『小銃』)、『星』ではアメリカ人との混血の日本軍人が軍規律を皮肉る。軍隊の中では「荒唐無稽な感情こそ、むしろあたりまえだ」と譲次(=ジョージ)は語るが、<極限状況の非現実さ>には、ユーモアさえ漂う。↓2014/12/05
空猫
40
【第32回芥川賞】短編集。「アメリカンスクール」とは米国占領軍が在日米人の子供の教育のために建てた学校のこと。そこへ日本人英語教師30人が何キロも歩いて見学にやらされる。米国との格差に卑屈になりながらも憧れもあり、英語教師としてのプライドもあり。皆真剣で真面目なのに何故か滑稽で。野坂氏の『アメリカひじき』より自虐的。どれも大戦の傷が生々しい話ばかりだった。…日本人が外人みたいに英語を話すなんて…外人みたいになってしまう。そんな恥ずかしい…(p259)。言い回しが独特でおいらには合わなかった。斜め読み。2022/03/18