内容説明
フランスから帰国した栄一は、明治新政府の招きで大蔵省に入り、国づくりの熱っぽい雰囲気の中で活躍するが、やがて藩閥の対立から野に下り、かねてからの夢であった合体組織(株式会社)を日本に根づかせるべく歩みはじめる…。一農夫の出身であり、いずれの藩閥にも属さなかったにもかかわらず、いかにして維新の元勲と肩をならべる最高指導者となっていったかをたどる。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
三代目 びあだいまおう
295
私的、ものすごく好きな歴史小説でした!誰もが血沸き肉騒ぐ明治維新、農民の出で薩長土肥いずれの藩閥にも属さなかったのに、近代日本の礎を築き今のこの国の経済の基盤を創った偉人、渋沢栄一の生き方!伊藤、大隈、大久保、井上、明治維新後の、今に連なる国家創成を担った者達の息吹き、信念、行動理念が伝わってくる!「剣」で日本を変えた維新志士、「論語と算盤」で世界に冠たる日本の経済を創った栄一!凄く貴重な小説です!全ビジネス幹部必読の名著!大変読みやすく、社会生活で大切にすべき『何か』に気付かされる素晴らしい作品‼️🙇2020/06/26
サンダーバード@怪しいグルメ探検隊・隊鳥
101
前半部分は自分が何をすべきか模索していた感があったが、明治維新後は日本の産業、実業の育成と言う大きなテーマに邁進する渋沢。合本(株式会社)と言う考え方にこだわり、独裁ではない新しい姿を描こうとする。それにしても、彼が懸命になって日本の産業を興そうとして奮戦していたのはまだ30代!時の政府の中心人物達も同世代が多い。本当に若い国であったのだなあ。★★★+2021/04/14
sayan
81
本書の解説にもあるが筆写の城山三郎らしく「経済」視点がふんだんに盛り込まれた渋沢栄一の「人格形成」、「国家形成」、そして「組織形成」がスピード感がある文章で表現されていて大変刺激的だった。p.121西郷隆盛との「入るを量って出ずるを成す」という根本的な考え方を軸に、p.179「・・・経済と道徳は一致できる・・・」と今で言う「社会的」投資(→渋沢直系の方が進めるsocial commonsなど)。また、p.350-360で繰り広げられる岩崎弥太郎との「事業」を推進する組織哲学のぶつけ合いが非常に面白かった。2015/12/06
shincha
74
血洗村の農家で生まれ、尊王攘夷の獅子となり、一橋慶喜の家臣となり、武士となり、建白魔と呼ばれ、維新後の政府に仕え、大隈重信、大久保利通、井上馨、伊藤博文ら明治の重鎮たちと喧々諤々とやりあい、そして民間でも三井、三菱(岩崎)、小野、大倉などとぶつかり、手を取り合い、殖産興業に人生をかけた渋沢栄一。『雄気堂々、斗牛を貫く』を生涯その態度を失わず、様々な誘惑、思惑、横やり、中傷、障害にも負けず、民業の発展に尽くした。今の日本の礎を築いた最大の功労者。今、一万円札になってどう感じているだろう?面白かった!2024/07/22
まつうら
62
(上巻のつづき)ヨーロッパから帰国した後は、大隈重信に請われ、新政府の高官となるが、大久保利通とのいざこざで辞去してしまう。たしか、江上剛の「クロカネの道をゆく」にも大久保利通が出てきて、政府内でだれかといざこざを起こしているくだりがあった。大久保利通のことは良く知らないが、どうしてこんなに敵が多いのかと思うと、ちょっと興味がわいてきた。 それと、政府を辞去したあとの渋沢栄一は、多くの事業にかかわっていくが、それらのエピソードをもっと詳しく知りたいと思った。
-
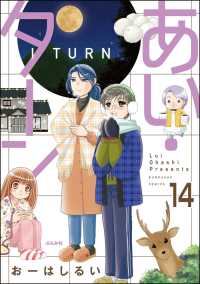
- 電子書籍
- あい・ターン(分冊版) 【第14話】
-

- DVD
- 潜水艦ろ号 未だ浮上せず






