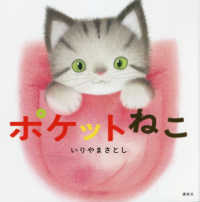内容説明
「大半の人が…」と言う時、あなたは何割の人を思い浮べていますか?中国語では大半は九割、多半が七割、一半が五割、そして小半が四割と、ちゃんと決っているそうです。それではだいたいは?物事をなるべくはっきり表現しようとする他の言語と違い、日本語は、あいまいさをむしろ良しとしているようです。何気なく使っている言葉を通して、日本的性格とは何かを考えてみましょう。
目次
よろしく
やっぱり
虫がいい
どうせ
いい加減
いいえ
お世話さま
しとしと
こころ
わたし
気のせい
まあまあ
ということ
春ガキタ
おもてとうら
あげくの果て
かみさん
ええじゃないか
もったいない
ざっくばらん
どうも
意地
参った、参った
かたづける
1 ~ 1件/全1件
- 評価
電子化待ちタイトル本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
9
普段何気なく使用している言葉が様々な意味を持っているということをじっくりと論じてくれています。ああこの言葉もこのような使い方、あるいは意味を持つこともあるのだということをわかりやすい言葉で説明しています。日本語にとっての目からうろこのような感じがしました。2013/06/21
せぴあ
8
普段使っている言葉をこんなに深く掘り下げて語れるのは凄い。国語教師としてとても面白かった。2018/03/14
Ted
8
'88年3月刊。(底本'85年3月)△「やっぱり」「どうも」「よろしく」など日本独特の言葉を取り上げ、外国語への翻訳がなぜ難しいか、その成り立ちから日本人の心性まで掘り下げて考察する24章。言語学者ではなく記者出身の評論家なのであくまでエッセイとして楽しむのが妥当。この当時は比較文化論が流行っていたのだろうが、学問的根拠に基かない個人的な想像や勝手な思い込みの入りやすい危うさがこの分野にはあるので注意して読む必要がある。また、「我々日本人は…」と安易に一括りにしてしまう点は感心しない。日本人もいろいろだ。2013/12/04
舟華
7
良くも悪くも曖昧さが魅力の日本語。普段全く違和感なく使っている言葉をピックアップして掘り下げてくれる。より曖昧さが深まって「そりゃ日本語を勉強する海外の方が難しがるわ!」と納得。ひとつひとつの言葉をもう少ししっかり見つめながら生活していきたい。昭和に出た本なので今では少し違う部分があるかもしれないがそこは気にしない。よい本。2022/02/04
yo
7
いかにも日本的な表現を取り上げ、その語源や背後に潜む日本的な感性を探る。一冊読み通して感じたのは、正確に外国語に訳せない日本語がこんなにも日常には溢れているということと、日本人が英語を苦手としていることは関連があるのではないか、ということ。いざ喋ろうとしても、「どうも」って言えないし、「よろしく」とも言えない。別にI'm glad to see you.と思ってるわけじゃないのに、本当はよろしくって言いたいのに、そういわざるを得ない。なんかそんなことを考えさせられるし、面白い本でした。2016/05/11
-
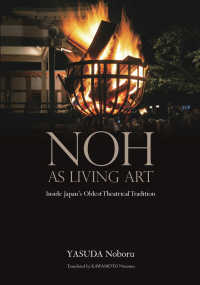
- 電子書籍
- Noh as Living Art: …
-
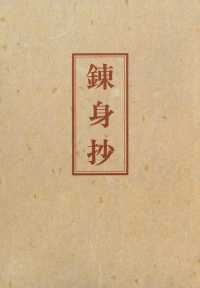
- 電子書籍
- 錬身抄