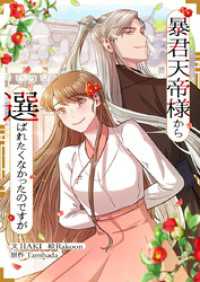出版社内容情報
貧困にあえぎながらも、向上心を失わず強く生きる一人の女性――日記風に書きとめた雑記帳をもとに構成した、著者の若き日の自伝。
第一次世界大戦後の困難な時代を背景に、一人の若い女性が飢えと貧困にあえぎ、下女、女中、カフェーの女給と職を転々としながらも、向上心を失うことなく強く生きる姿を描く。大正11年から5年間、日記ふうに書きとめた雑記帳をもとにまとめた著者の若き日の自叙伝。本書には、昭和5年に刊行された『放浪記』『続放浪記』、敗戦後に発表された『放浪記第三部』を併せて収めた。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
307
冒頭近く、歌の引用に続いて「私は宿命的に放浪者である。私は古里を持たない。―中略―故郷にいれられなかつた両親を持つ私は、したがつて旅が古里であった」の名高いくだりがある。これは、この作品の題名の由来を物語るばかりではなく、この作品全体の、そして林芙美子そのものを表象しているだろう。大正11年、彼女の19歳の時からの行状が日記体で綴られる。当然、フィクションも含まれるだろうが、そのスタイルとともに、また全てを開放的に語ろうとする、その文体と相まって強いリアリティを持つ作品である。東京をはじめ、尾道などを⇒2025/09/15
藤月はな(灯れ松明の火)
115
故、森光子さんの舞台での一場面が先行してしまい、明るいイメージを勝手に持っていたこの作品。ところが読んでみるとワーキングプア小説の先駆けだったので驚いた。しかもワーキングプアやダメンズ、男と暮らす事が安定への道信仰は今も殆ど、変わっていない所に苦笑。もうね、その日その日の浮草暮らしで生活の不安と何もない自分が嫌になるとか、家族にお金をせびる事になって申し訳ない気持ちとか、偉そうな口ばかりのヒモ男に寄生されても追い出せない悲しさとか、美味しいものや好きなものでちゃっかり、元気になるとかに共感せざるを得ません2018/12/10
やいっち
76
読了後、巻末の年譜を眺めた。墓所は、中野区上高田の寺だとか。なんと、我輩が上京して初めて頃に居住したのが上高田のアパートだった。当時は、林芙美子は全く読んでなかった…眼中になかった。惜しい。知ってたら墓参したのに。…ということで、感想はあとで。とんでもなく貧乏臭く辛気臭いのだが、貧困に喘ぎながらも、書くことへの執念が身を決定的に誤らせることをさせなかった。書くこととは何だ? 2024/07/22
優希
56
貧困に襲われても、向上心を忘れない姿が刺さりました。様々な職業を転々としながら必死で生きていく様子が日記風に書かれているので、単なる自叙伝としてではなく、現状が迫ってくるようでした。どこまでもヒリヒリするのに引き込まれずにいられませんでした。2022/03/30
ころこ
54
日記形式で前後関係が分断されているので、登場人物やプロットは関係ない。要は一人称さえ追っていれば読めてしまう。読み始めから長く掛かったとしても鮮度を失わない。女性読者を獲得したのは自分に重ねたことと、家事の合間に読むことができたことが背景にあったのではないか。貧乏によって哀切が漂うので誤解を生むが、日常系のマンガが近い。文末をまくるような文体に特徴がある。要所に登場する詩はこの文体から加速度をつけて離陸して書かれている。一人称の巧みさが現実から逃れる瞬間をつくり、少しの自由をみせてくれるのが作者の魅力だ。2024/07/09