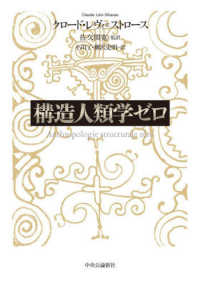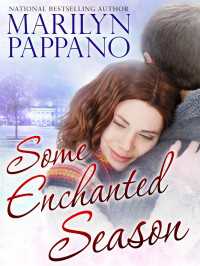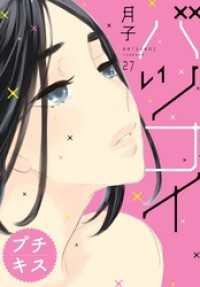内容説明
十三歳の登は自室の抽斗奥に小さな穴を発見した。穴から覗く隣室の母の姿は艶めかしい。晩夏には、母が航海士の竜二とまぐわう姿を目撃する。竜二の、死すら厭わぬ船乗り精神と屈強な肉体に憧れる登にとって、彼が海を捨て母を選び、登の父となる生ぬるい未来は屈辱だった。彼を英雄に戻すため、登は仲間と悪魔的計画を立てる。大人社会の綻びを突く衝撃の長編。横浜港で船員らに取材し一気に書き上げた。38歳の三島が子供世代の目で描く大人の虚妄。
著者等紹介
三島由紀夫[ミシマユキオ]
1925‐1970。東京生れ。本名、平岡公威。1947(昭和22)年東大法学部を卒業後、大蔵省に勤務するも9ヶ月で退職、執筆生活に入る。’49年、最初の書き下ろし長編『仮面の告白』を刊行、作家としての地位を確立。主な著書に、’54年『潮騒』(新潮社文学賞)、’56年『金閣寺』(読売文学賞)、’65年『サド侯爵夫人』(芸術祭賞)等。’70年11月25日、『豊饒の海』第四巻「天人五衰」の最終回原稿を書き上げた後、自衛隊市ヶ谷駐屯地で自決。ミシマ文学は諸外国語に翻訳され、全世界で愛読される(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
むーちゃん
62
ただの官能な内容かと思いきや、なんか崇高な感じも残しつつ… あと何冊か三島由紀夫チャレンジしてみます。 2025/06/17
けぴ
52
新版なので文字が大きく読みやすい。父を亡くし母と二人暮らしの登は中学生。船乗りの竜二と良い仲になる母。二人の夜の生活を隙間から覗きこむ登。谷崎潤一郎っぽい変態さを感じながら物語は進行。やがて竜二と再婚を決意する母。ある時、夜の生活を登が覗いていることに気付く。母と竜二に叱られる登。罰を与えるとして登と中学生の仲間は竜二を誘い出し、毒入り紅茶を飲ませるところで幕が閉じられる。中編ながら読み応えあるストーリーでした!2021/05/30
NICKNAME
35
思ったより短く他の作品群と比べ内容的にも薄く感じられる作品であった。想像していたエンディングと全く違い何だかあっけない終わり方である。ただその締め括りの最後の一文が三島作品で奔馬の最後を彷彿させる。結局強く引き込まれないまま、短い作品であるのに結構ダラダラ読んでしまった。三島にもこういう作品があるというのがある意味新鮮ではある。2022/03/04
Shun
32
登少年は抽斗の奥に隣室を覗き見られる小さな穴を発見し、ある日母が連れてきた若い航海士の男との情事を目撃してしまう。少年は船で働く航海士に英雄的憧れを抱いていたが、夫に先立たれた母とやがて再婚するであろうこの男に登は一方的な憎しみを抱いていく。登にとって海を離れて陸で安穏とした家庭を築くのは堕落と映り、また同じく崇高な理念を共に懐いた少年グループの間でも大人たちへの軽蔑心からこの者を罰せねばならぬと意志を同じくしてしまう。恐るべき子供たちによって男の運命は決し、最後の一文に男のただならぬ栄光の影を見た。2025/02/11
しんすけ
22
三島由紀夫最晩年の作品と云って良い。 この後に白鳥の歌として『豊饒の海』シリーズを残すが、『午後の曳航』ほどの香ばしさは失せていた。 十三歳の登という少年は主役のようだが、狂言回しにしか観えないことが時折ある。この少年が覗き見る母の姿が艶めかしいからだろう。 本書の初読時、ぼくは十七歳だったはず。その時は登の母の美しさを創造し、その創造に陶酔しながら読んでいた。 そしてぼくの耳もとで、ひばりの「港町十三番地」が聞こえていたような気もする。2022/04/21