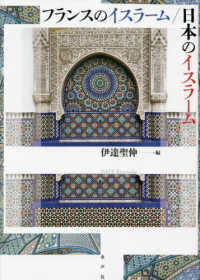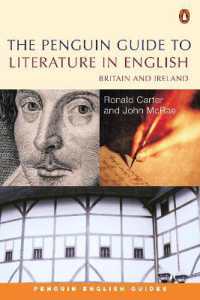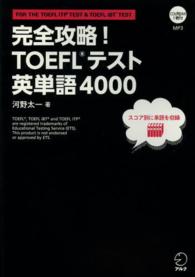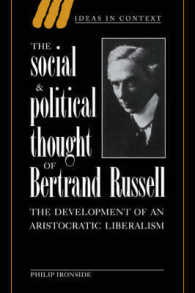内容説明
親友を裏切って恋人を得たが、親友が自殺したために罪悪感に苦しみ、自らも死を選ぶ孤独な明治の知識人の内面を描いた作品。鎌倉の海岸で出会った“先生”という主人公の不思議な魅力にとりつかれた学生の眼から間接的に主人公が描かれる前半と、後半の主人公の告白体との対照が効果的で、“我執”の主題を抑制された透明な文体で展開した後期三部作の終局をなす秀作である。
著者等紹介
夏目漱石[ナツメソウセキ]
1867‐1916。江戸牛込馬場下(現在の新宿区喜久井町)に生れる。帝国大学英文科卒。松山中学、五高等で英語を教え、英国に留学した。留学中は極度の神経症に悩まされたという。帰国後、一高、東大で教鞭をとる。1905(明治38)年、「吾輩は猫である」を発表し大評判となる。翌年には「坊っちゃん」「草枕」など次々と話題作を発表。’07年、東大を辞し、新聞社に入社して創作に専念。『三四郎』『それから』『行人』『こころ』等、日本文学史に輝く数々の傑作を著した。最後の大作『明暗』執筆中に胃潰瘍が悪化し永眠。享年50
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 5件/全5件
- 評価
新聞書評(2013年3月~2014年12月)の本棚
- 評価
テレビで紹介された本・雑誌の本棚
- 評価
新聞書評(2016年)の本棚
- 評価
新聞書評(2015年)の本棚
- 評価
This is my本棚
-
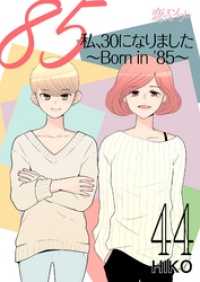
- 電子書籍
- 私、30になりました。~Born in…