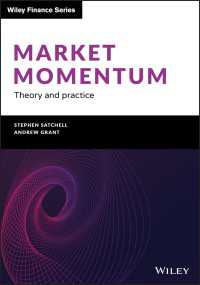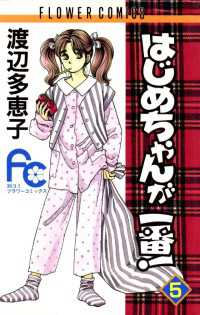内容説明
「もののあはれ」の説は、単に「源氏」研究の学説に留まるものではなかった。宣長において、それは、実人生の情を論じる際にも一貫していた。ひたすら宣長の肉声に耳を傾けながら、その徹底した学問と人生の態度を味わい、いかに生くべきかを究めた本書は、同時に現代最高の知性、小林秀雄の思索の到達点でもあった。本篇刊行後に上梓された「本居宣長補記」を併録する待望の文庫版。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
双海(ふたみ)
25
上巻を読み終えたその日から本書の再読を始めました。徂徠を論じたところが私には難解でした。上巻と同様に宣長、徂徠、秋成などの原文からの引用が多いのがありがたい。 巻末には江藤淳との対談も。小林:「いまの学問は割り切れるところだけで学問をしているから、学問の喜びというものも生れない。情(こころ)が脱落しているからね。(中略)情を欠くのは、人間を欠く事だからな。」2015/12/30
弥勒
13
「本居宣長」を読み終えて、最後に江藤淳氏と筆者との対話が収録されているが、やはり私も宣長のことをわかったつもりで本当はわかっていなかったことがわかった。というのも、宣長の遺言がさすところの彼の思想の極致というものを感じることができなかったからだ。だから、何度でも読んで理解できるまでになりたいと思った。2015/08/27
Ken-Ken
6
「未だ文字も知らぬ長い間の言伝えの世で、日本人は、生きた己れの言語組織を、既に完成していたという事実につき、宣長ほど明晰な観念を持っている学者はいなかった。」古事記の神代の物語を読むには、論理的・実証的な思考を離れ、古典を外から解釈するのを止め、荒唐無稽に見える古伝説の一切を信じ、古代人の認識の世界を生きる必要がある。宣長は源氏物語で開眼した「もののあはれ」の心をもって古事記と向き合ったそうな。我々からは余りにも遠い感受性であり、ほとんど理解できなかったが、ここまで到達できれば、人生の甲斐がありそうだ。2016/07/18
Omelette
5
これは「日本語で日本語を語る」言語学の本なのかもしれない。ラングという言葉さえ使われていないが、ソシュール言語学や、ウィトゲンシュタインの言語哲学が透けて見えるようだった。ちなみに、本文のなかで使われている、西洋語由来のカタカナ語は、「タクシイ」「メタフォーア」「アルファベット」「シンタックス」「ニュアンス」など、全部で10にも満たないと思う。思想的にはベルクソンの『創造的進化』などを知っていると頭に入りやすい2009/12/25
Asakura Arata
4
本居宣長という人は言葉の世界との「環融体験」を具現化しようとしていたように思う。そもそも話し言葉だけの時代はそのようなことが当たり前だったのではないか。2025/05/22