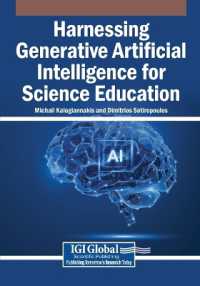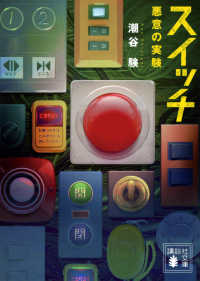内容説明
両親を早くに失った私は、幼い頃から祖父を一人で介護していた。私が十六歳の時に祖父が亡くなり、火葬され…。自伝的な「骨拾い」のほか、「伊豆の踊子」の原形をなす「指環」、謎めいた高貴な少女が馬車を追いかける「夏の靴」、砕け散ってしまった観音像を巡る「弱き器」など、四十年以上にわたり書き続けられた豊穣なる掌編小説122編。神秘、幻想、美的感受性等、川端文学の粋が凝縮されている。
著者等紹介
川端康成[カワバタヤスナリ]
1899(明治32)年、大阪生れ。東京帝国大学国文学科卒業。一高時代の1918(大正7)年の秋に初めて伊豆へ旅行。以降約10年間にわたり、毎年伊豆湯ケ島に長期滞在する。菊池寛の了解を得て’21年、第六次「新思潮」を発刊。新感覚派作家として独自の文学を貫いた。’68(昭和43)年ノーベル文学賞受賞。’72年4月16日、逗子の仕事部屋で自死(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
こーた
152
二十代の頃から四十年以上にわたって書き継がれた文体練習。練習?いやいや、これぞ川端の真骨頂だ。長くて十頁、短いもので二頁ほどの掌編、超短編、ショートショートが百篇以上ずらりと並ぶ。一行で世界を創りだす。その世界が、次の一行で暗転する。無数の世界が星々の如く撚り集まって宇宙を形成する。川端の追い求めた魔界は、ひょっとするとこの星と星の間の、何もない空間に横たわっているのかもしれない。だから小説はこのサイズでなければならない。⇒2025/04/15
ykmmr (^_^)
127
川端のショート&ショート的な小説集。後の『伊豆の踊り子』に結びつく作品もあるので、これを読む読者だけではなく、彼自身も『小説家』としての処女作みたいな感じなんだろう。しかし、比較的読みやすい川端文学とは裏腹に、短いのに意外に難読で数も多い為、読まされた感がある。そんな状態なので、「印象に残るのはどれか?」と言われると分からない状態となってしまった。読みやすいのも理由と言える、ファンである川端に、初めて振り回されてしまった。ただ、次に読むのは…再読であるが、『伊豆の踊り子』に決めた。2022/06/08
ともっこ
29
8月末から一日一篇(時に一日二篇)ずつ読み始め、2022年12月23日に完走。 短いがゆえに解釈が難しいものが多く、決して楽しいばかりの読書ではなかったが、短篇の一篇一篇を毎日こんなに真剣に読み込んだのは初めてで、貴重な読書体験だった。2022/12/23
まさ
28
『掌の小説』なので気楽に読むことができるかと思いきや、なかなか読み応えがありました。1編が数ページのものがほとんどとはいえ、それが100以上あり、奥深いものばかり。なかなか、次、次、とはいかない。解説で小川洋子さんが話したとおり、一続きの広大な世界をさ迷い歩いたかのよう。なにはともあれ、川端康成の世界を彷徨い、いつまでも巡り巡っている気分。2023/06/02
しんすけ
26
川端康成は、あの大きな賞に殺されたのではないだろうか。 50数年ぶりに再会した川端康成である。 生前から川端康成には悲運がつきまとっていたように思える。 文章読本の依頼は受けたものの書き進められず、代筆を依頼したという噂が流れていた。 川端康成には文章を縦横無盡に操る才はなく、抒情世界を美しく語る人だった。 さらに源氏物語の現代語訳に挑んだものの、手に追えず断念するしかなかった。 川端康成には、三島由紀夫や谷崎潤一郎の絢爛豪華な世界は似合わない。 それを知れば『掌の小説』の囁かな美しさに、浸れると思う。2022/07/16
-

- DVD
- テレタビーズのたからもの