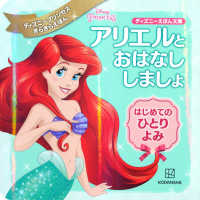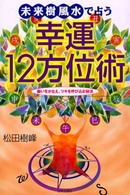出版社内容情報
小学校「特別活動」の精神と本質がわかる本
「日本の教育は人づくりにある」といわれるが、若い教師は、学校や学級の人間関係や集団性をいかに高めるかに苦心している現実がある。
本書は、現役の文部科学省教科調査官として、全国の小中学校で特別活動の在り方を講演、指導する著者が、独自のポートフォリオと図解式で、「どのようにしたら子どもたちの人間関係が築かれ、集団づくりがうまくいくか」、「小学校は社会の縮図であり人間関係を形成する大事な準備期間であること」など、小学校での特別活動の喫緊の課題と必要性を具体的な実践事例で紹介します。
なぜ、今、「いじめ」が起き、その予防薬としての特別活動が有効であり、小学校での特別活動で人間関係の構築が必要なのかを詳細に解説します。大人になって、人間関係で失敗しないためにも、小学校時代の特別活動は、コミュニケーション能力と人間関係を築く上で教師の関わりが必要であり、その役割を考える教育単行本になるでしょう。
はじめに 6
第1章 同じ目標に向かう集団づくり 7
第2章 学級活動(1)生活づくりのための学級会 27
第3章 学級活動(1)生活づくりのための係活動・集会活動 77
第4章 学級活動(2)自己指導能力を育てる授業 101
第5章 いじめ予防薬としての特別活動 109
巻末資料 148
杉田 洋[スギタ ヒロシ]
著・文・その他
内容説明
若い先生に向けて、特別活動担当の文部科学省教科調査官が特別活動の実践的な指導法のノウハウをわかりやすく伝授!いじめ問題の予防薬としての特別活動など、喫緊の課題についても指摘する。
目次
第1章 同じ目標に向かう集団づくり(特別活動の教育課程上の役割;大震災での避難所生活に特別活動の原点を見る ほか)
第2章 学級活動(1)生活づくりのための学級会(学級活動(1)学級や学校の生活づくりの改善のポイント
活動計画をつくる ほか)
第3章 学級活動(1)生活づくりのための係活動・集会活動(係活動で楽しい学級をつくる;集会活動を成功させる要点 ほか)
第4章 学級活動(2)自己指導能力を育てる授業(学級活動(2)を成功させる8つのポイント(食の指導を例に))
第5章 いじめ予防薬としての特別活動(いじめに強い学級をどうつくるか;いじめを生まない学級づくり ほか)
著者等紹介
杉田洋[スギタヒロシ]
文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官。国立教育政策研究所教育課程研究センター教育課程調査官(小学校・特別活動担当)。日本特別活動研究会理事。浦和市立小学校教諭、教育委員会を経て、平成16年4月より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
江口 浩平@教育委員会
totuboy
jotadanobu
mori