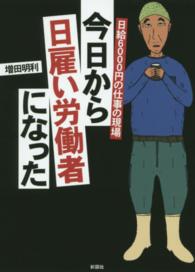出版社内容情報
教育改革最前線。うちの子はどうなる?
学習指導要領が約10年ぶりに改訂され、2020年度より小学校、2021年度より中学校で実施。かたや大学入試制度改革は迷走し、日本の教育が大きな転換期を迎えている。
一方、国際経営開発研究所が発表した、主要63か国の「世界競争力ランキング2019」では、日本は順位を5つ下げ、30位に急落。東アジアの中でもシンガポールや中国、台湾、タイ、韓国の後塵を拝し、もはや日本型教育では、国際社会で通用しないことは明らかだ。
さらに近い将来、現在ある職業の大部分がAIに取って代わられるといわれる。
「いい学校に入れば、いい生活が送れる」時代は終わった。
こうした危機的状況にいち早く気づき、子ども主体の教育に舵をきってきた人がいる。
1人は「校則なくした中学校」の校長、もう1人は名門男子中高一貫校の理事長、最後の1人は子育てやいじめ問題に真正面から取り組んできた教育評論家だ。
立場の異なる教育最前線の3人が、意外と気づきにくい「子どもが生まれ持つ本来の特性」を解きながら、才能を伸ばしていく方法を明らかにする。
学校に息苦しさを感じる親も子も、教壇に立つ先生も、ぜひ読んでほしい1冊です!
【編集担当からのおすすめ情報】
著者の1人、西郷孝彦さんが校長を務める東京・世田谷区立桜丘中学校は、校則はなく服装も自由、定期テストが廃止されたことで、その名が全国区となりました。
同校は、こうした「学校の当たり前」を生徒と一緒に見直しただけでなく、教員と生徒の信頼関係に重きを置き、子どもが心の底から安心できる環境づくりに取り組んできました。
結果、生徒の自己肯定感や非認知能力が上がり、同時に学力も飛躍的に向上。このことに、多くの人が関心を寄せています。
2019年冬、桜丘中学校保護者の有志が、西郷校長と教育評論家の尾木直樹さん、麻布学園理事長の吉原毅さんを招いて教育に関するトークイベントを開催しました。
事前予約には約1000人の申し込みがあり、なんとキャンセル待ちまで発生しました。
イベント終了後のアンケートは、回答率が7割を超え、そのほとんどに悩みや質問が記されていたことは、昨今の教育不安を浮き彫りにしたといえます。
本著では、そうした不安を1つでも解消してほしいという願いから、再び3人が集まり、いまこそ不可欠な教育についての知恵を出し合いました。
尾木さんは、近い将来を見据えた新しい学びの具体例を挙げています。吉原さんは経済界が抱える問題点を解消するため身につけるべき教育を語っています。西郷校長は、ともすると陥りがちな教育の落とし穴とその脱却するすべを指し示しています。
依然としていじめや不登校の問題は横たわり、大学入試制度さえ右往左往する時代。
子育てに迷わない人のほうが少ないはずです。
不安脱却の手がかりを、ぜひ本著で見つけてほしいと思いま
内容説明
「勉強しろ」の一言は“教育虐待”だった!父親と母親の「過干渉」に大きな違いがあった。校則も定期テストもない中学校で育まれる傑出した力を、データが実証!!これからは「自分の頭で考えて行動できる子ども」が一番強い!…いま、話題の中学校に学ぶ最新教育論。AI、大学入試改革、インクルーシブ教育、非認知能力、アクティブ・ラーニング…押さえておくべき用語解説つき。
目次
第1章 “みんなが主役”の学校づくり(「廊下」という居場所;生きづらい子どもたち ほか)
第2章 学校の“いま”、家庭の“いま”(「同調圧力」に苦しむ子どもたち;校則をなくしたらいじめもなくなった ほか)
第3章 可能性が広がる学校の“ミライ”(必要とされる「生きる力」;損得勘定で動く人たち ほか)
第4章 親の“不安”、その先の“希望”‐親の声・子どもの気持ち―イベントアンケートからわかったこと(中学校に投じられた“一石”;8割の参加者が思いを綴ったアンケート ほか)
著者等紹介
西郷孝彦[サイゴウタカヒコ]
1954年横浜生まれ。2010年、世田谷区立桜丘中学校長に就任。2020年3月に退職
尾木直樹[オギナオキ]
1947年滋賀県生まれ。教育評論家、法政大学名誉教授、臨床教育研究所「虹」所長。愛称は「尾木ママ」
吉原毅[ヨシワラツヨシ]
1955年東京都生まれ。麻布学園理事長、城南信用金庫顧問。2017年に全国組織「原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟」を設立、会長に就任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ムーミン
turtle
貧家ピー
あーちょ
乱読家 護る会支持!


![婦人公論 2021年5月25日号 No.1565[〈私たちのノンフィクション〉幸せは涙のあとに] 婦人公論](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0994731.jpg)