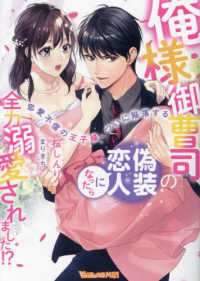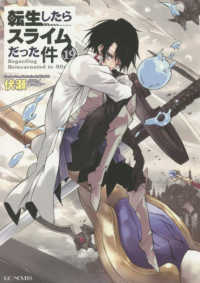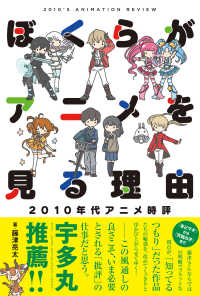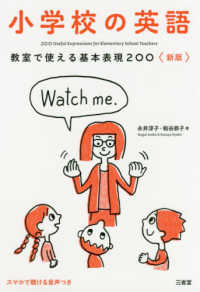出版社内容情報
名画に見る「闇」がつくった西洋絵画の歴史
17世紀西洋絵画の巨匠ラ・トゥールやレンブラント、フェルメールといった、日本で人気の高い画家に共通している特徴は、精神性の高い、静謐で幽玄な光と闇の描写にあります。それらの画家の絵画に描かれた深く豊かな闇の表現は、『陰影礼賛』を素直に理解し受け入れる感性をもった日本人にとっては、親しみやすく感じられるものです。しかし、「闇」を描くことは、西洋絵画の歴史の中では、極めて革新的な出来事でした。なぜなら、中世以降、西洋絵画は神を讃えることを目的に描かれたため、世界を照らし出す光に包まれているべきものだったからです。
本書では、イタリア・ルネサンスの巨匠レオナルド・ダ・ヴィンチによって確立された革新的な「闇」の表現が、バロック絵画の先駆者カラヴァッジョによる光と闇がドラマティックに交錯する絵画を経て、いかにしてラ・トゥール、レンブラント、フェルメールらの静謐で精神的な絵画を生み出していったのか、西洋絵画における「闇」の歴史をたどります。わかりやすい文章と数多くの美麗で魅力的な図版によって、初心者も経験者もともに、これまでになかった斬新な視点から西洋絵画の歴史が楽しく読める書物となっています。
宮下 規久朗[ミヤシタ キクロウ]
著・文・その他
内容説明
ルネサンスの巨匠レオナルド・ダ・ヴィンチが確立した革新的な「闇」の表現が、バロック絵画の先駆者カラヴァッジョによる光と闇のドラマを経て、いかにして静謐で精神的な絵画へと成熟していったのか、西洋名画を育んだ「闇」の歴史を、西洋美術史界屈指の「語り部」である著者が、美麗な図版とともにわかりやすく解説。
目次
第1章 闇の芸術の誕生―レオナルド・ダ・ヴィンチとルネサンスの巨匠たち
第2章 光と闇の相克―カラヴァッジョ
第3章 ヨーロッパに広がる闇―カラヴァッジョ派とバロックの巨匠たち
第4章 心の闇を照らす焔―ラ・トゥール
第5章 闇に輝く黄金の光―レンブラント
第6章 闇を溶かす光―フェルメール
第7章 闇の近代―光と闇の継承者たち
- 評価
-





かもしか堂の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
KAZOO
kaori
ホークス
sakanarui2