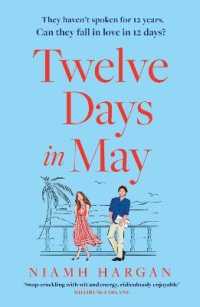出版社内容情報
寛政六年から七年にかけて、百数十種もの役者絵・相撲絵などを残しながら、こつ然として姿を消した謎の浮世絵師東洲斎写楽。その独特の画風を究明しつつ、人間写楽を考察する。
私たち日本人の数千年の歴史をいろどる華麗な美術品の数々?それは、如実に時代を反映しながらも、なお時代を越えて私たちの胸に迫ってきます。こうした日本美術の枠を、ひとりでも多くの人に伝えたい……との願いから生まれた価値あるシリーズ、それがブック・オブ・ブックスです。親しみやすい編集と最高水準をいく印刷技術、しかもお求めやすい価格と、まさに三拍子そろった本書は、70年代を代表する理想のホームライブラリー。ぜひ一家に一シリーズをおそなえください。ブック・オブ・ブックスを開くとき、あなたの家のお茶の間は、数千年の歴史を秘めた美術館に生まれ変わります。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
紫
2
約5年ぶりの再読。改めて読み返したところ、楢崎宗重先生、美術史家らしく浮世絵の成り立ちや肖像画の変遷といった通史的な話題は滔々と論じてみせる一方で、写楽単独の研究や、個々の別人説の内容については関心もないのか紹介がとっても雑。巻末には五人の別人説論者との対談が収録されているんですが、楢崎先生のリアクションは社交辞令に終始しておりまして、写楽の話題については対談相手の方がずっと詳しいような……。美術史全体の上では写楽の正体なんて重要ではないから誰だっていいや、ということになるのでしょうか?2023/05/10
紫
1
1974年刊行。約40年前の東洲斎写楽研究の水準を勉強するおつもりでお読みください。前半120ページは図版80点+解説。掲載順はランダムで、基準がよく分かりません。中盤40ページは著者楢崎宗重による写楽解説(当時の通説?)を挟み、後半40ページは別人説論者五人(福富太郎・由良哲次・榎本雄斎・中村正義・近藤喜博)との対談。「ぼくは学者ではないから、まちがっていても責任をとらなくていい」(!)と豪語する福富氏をはじめ、アイデアを楽しんでいる榎本・中村とは違い、由良・近藤はどうやらガチ勢であります…。星3つ。2018/08/11