出版社内容情報
「鎌倉幕府を倒せ」。東国の武家政権に対して、京都では強烈な個性をもった後醍醐天皇が即位した。世は「悪党」の時代。彼らの行動は大きなうねりとなって、幕府を崩壊に追いやる。足利氏があらためて京都に開いた室町幕府は、内乱期の社会をにぎやかに彩る「婆娑羅」のエネルギーを巧みに取り込み、公家たちをも吸収していく。しかし、その基盤はもろく、やがて求心力を失い、下剋上の世が到来する。一方、能・狂言をはじめとする芸能や、禅宗、「わび・さび」といった美意識など、日本文化を代表するものを生みはぐくんだこの社会には、広く「庶民」の参加がみられた。視点をできるだけ低く、地方にも目を配りながら、南北朝・室町時代を再構成した。
安田 次郎[ヤスダ ツグオ]
著・文・その他
内容説明
終わりのない戦乱新しい価値観が人びとを躍動させる。南北朝の争乱から応仁の乱まで闘争する社会を描く。
目次
第1章 弓矢から打物へ
第2章 京都の幕府
第3章 婆娑羅
第4章 中夏無為の代へ
第5章 日本国王
第6章 合議と専制
第7章 飢饉・一揆・合戦
第8章 応仁の乱
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
26
鎌倉幕府滅亡から応仁の乱までが書かれています。今回読んで面白かったのはバサラという章を設けてまるまる説明してくれていることです。また藝術が能をはじめとして結構盛んに行われていることに興味を持ちました。戦乱の世でも余裕があったのでしょうか?2014/11/27
shiggy
6
鎌倉末期から室町はひっちゃかめっちゃかでわかりにくい時代だが、丁寧な解説で少しわかるようになった。中世で影の薄い奈良の記述が奈良人としては面白かった。応仁の乱の本質はイマイチわからないままだが、10年も続いたのは突出した権力がなかったからだと理解できた。2020/12/30
鐵太郎
5
飢饉の時のセーフティネットとして人身売買をあげています。『安全装置と言うにはあまりにも過酷な方法だが、大きくみれば、食料のある場所、生存可能な状態へ、飢えている人々を移動することである。寛喜二年(1230)には稲や麦が不作だったので、蓄えられている食料が全体として激減したことは間違いないが、食料や富は偏在する。あるところになある。持てる者のところへ持たざるものが奴隷として買われていって命を永らえるのである。』人が生き残る理由、文化が継承さる理由を一つの解釈として得るためには、こんな考え方もあり、か。2008/09/22
だ~しな
3
ドラマ太平記など諸々の影響で今室町後期から、戦国時代までの流れが自分の中で熱いので、この本をチョイス。 特色すべき事として、教科書に省かれがちな何故そうした政策を行ったのか?という点を室町将軍などの為政者、関係者、幕府内外の力関係、その他の要因を詳しく説明してくれている。歴史とは大きな流れを俯瞰する学問なので、ここを面白く書ける良い一冊である。 個人的には言及されにくい義詮、義持時代の記述も多く、非常に嬉しい。あと各室町将軍の人間性を資料の中から読みとる考察が、歴史を紐解いていくなかで親近感が湧かせる。
へたれのけい
3
教科書の大まかな歴史の流れを分らないで読むには、ちと、無理があったかもしれない。それでも、全巻読み切りたい。がんばれよ!2018/02/16
-

- 電子書籍
- ライブダンジョン!【分冊版】 16 ド…
-

- 電子書籍
- レディ、ご一緒にいかがでしょうか【タテ…
-

- 電子書籍
- レディ、ご一緒にいかがでしょうか【タテ…
-
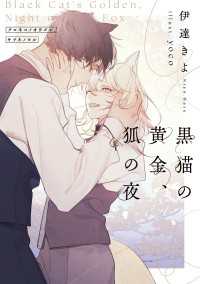
- 電子書籍
- 黒猫の黄金、狐の夜【電子特別版】 ルビ…
-

- 和書
- 松下幸之助散策・哲学の庭




