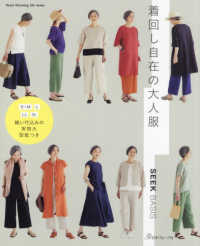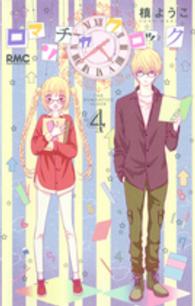出版社内容情報
"山人の存在を意識した柳田の民族学以前の構想""山人論""はなぜ後退したのか。『山の人生』で終焉した論考を検証する。"
あらゆるものが変容していく近代という時代のなかにあって、柳田国男は、日本という固有の歴史風土のなかで民俗学はいかにして可能かを問い続け、未知の領域に果敢に踏みこんでいった。そこにはいくとおりもの民俗学の可能性があった。しかし柳田は、前期に構想したその可能性を周縁のくらがりへうち棄て、常民中心の「一国民俗学」を体系化し、それによってわが国のすべての民俗事象を理解しようとした。柳田が「民俗学」を確立する過程で排除せざるをえなかった前期思想、とくに山人論はいまも埋もれたままである。柳田は山人論をどのように後退させ、「民俗学」へと転向していったのか。 著者は、柳田の「民俗学」以前へさかのぼり、柳田の思想の発生の現場に立って膨大なテクストを読み解くことによって、切りすてられた思想を掘り起こし、柳田の知の足跡に秘められたゆらぎと断層を浮き彫りにする。現代において、あるいは未来に向けて、柳田の思想は可能なのか、その限界と可能性を問う労作。
内容説明
『後狩詞記』『遠野物語』は生きている。それは柳田の常民の民俗学の原点であるとともに、まったく異質の方向を指し示す著作でもある。これらの物語発生の現場に立ち会って、柳田の思想の根源を考える。
目次
序章 物語の闇・遠野にて
第1章 椎葉より
第2章 血と漂泊
第3章 天然の力
第4章 山人その後
第5章 山人の誕生
第6章 稲の風景
第7章 平地人と常民