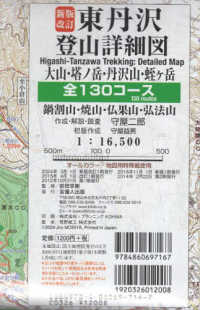内容説明
縄文の時代へと遡る源流。伝説、信仰、地名、方言から、民謡、演歌、宮沢賢治、吉里吉里国に至るまで、さまざまなモチーフを駆使して掘り起こされる東北の歴史と文化の基層。そこから立ち現われてくるのは、中央から“辺境”を眺めた時とは全く違う、新たなる日本の姿。“東北学”の提唱者と七賢人のユニークな対論を通して、「日本人とは何者か?」を改めて問い直す、東北からの日本再発見。
目次
第1章 東北の可能性(五木寛之×赤坂憲雄)
第2章 縄文の記憶を求めて(中沢新一×赤坂憲雄)
第3章 精神史の古層へ(谷川健一×赤坂憲雄)
第4章 蝦夷とはだれか(高橋克彦×赤坂憲雄)
第5章 はじまりの東北(高橋富雄×赤坂憲雄)
第6章 ふたたび吉里吉里へ(井上ひさし×赤坂憲雄)
第7章 生と死の風景から(山折哲雄×赤坂憲雄)
著者等紹介
赤坂憲雄[アカサカノリオ]
民俗学者。1953年、東京生まれ。東京大学文学部卒業。フィールドワークを続けながら、東北の歴史や文化を掘り起こし、“東北学”を提唱。現在、東北芸術工科大学大学院教授、同大学東北文化研究センター所長、福島県立博物館館長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
翔亀
50
気鋭の民俗学者だった赤坂憲雄さんが柳田国男との格闘を経て東北学を唱えてから20年近くたつだろうか。東北学以降の彼の著作は読んでないが、平泉のことを漁っていてふと気になり、この東北をテーマとした対談集を読んでみた。五木寛之とは「差別」、中沢新一とは「縄文」、谷川健一とは「アイヌと地名」、高橋克彦とは「蝦夷」、山折哲雄とは「死生観と宗教」をめぐって語る中で、現代日本が喪ってしまったものを東北(の歴史)の中から引き出そうとしている。それは差別なき東北であり、縄文の系譜を引いた東北であり、アイヌと価値観を共有す↓2017/05/24
misui
4
赤坂憲雄が提唱する東北学に関する7つの対談。縄文からの豊かな広がりを思えば、辺境として扱われてきた東北の視点で考えることの重要性がよく理解される。東北の古い風俗を伝えるとして度々言及されるイザベラ・バード、菅江真澄などにも興味を抱いた。2018/04/21
ヨシモト@更新の度にナイスつけるの止めてね
4
高橋克彦は『火怨』を書く際、征服者・坂上田村麻呂が東北で英雄視されている事実を無視できず、アテルイとの信頼関係という形で描かざるを得なかったという。アイヌモシリになぜか義経神社があるのと同じ心理か。「大同」という年号が鍵となるらしい。2015/07/01
がぁ
2
みんな東北に行ってみればいいんだよ。まずその地に足を踏み入れてみれば、そのすばらしさが少しでも届いてくる。対話集としては上質のものでした。2011/08/12
ひろみ
1
当たり前だけれども震災の前から東北はその広大で奥深い自然や山々を抱えて存在していた。そのことを思い知らされた。東北のおばあちゃんの聞き書きの件で、河童かと思ったら隣のあんちゃんだったというのがあるけれど、その、河童であり隣りの青年でもあるという感覚や、東北の人たちが見せる茶目っ気は一東北人として細胞の単位で理解できて、思わず泣いた。2014/04/12