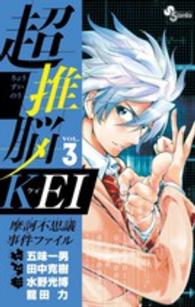出版社内容情報
復興の希望・伝説のラジオドラマの舞台裏
物語は高度成長期と呼ばれる昭和48年、『鐘の鳴る丘』に出演した当時小学生の一人、良仁への一本の電話から始まる。この日、戦後を代表する劇作家であり、『鐘の鳴る丘』の脚本家・菊井一夫が逝去。電話は菊井の葬儀の知らせだった。知らせを受けて菊井との記憶に思いを馳せる良仁の脳裏には、いつしか「緑の丘の赤い屋根 とんがり帽子の時計台…」と、少年少女たちの歌声が流れ始めていた。
昭和22年。ようやく給食が再開したものの、ほとんどの子どもがいつもお腹を空かせていた時代。東京・練馬区の小学校に通う良仁は親友の祐介と全力で遊びまわる日々を送っていた。そんなある日、良仁と祐介、そして、隣のクラスの実秋を含めた数名が、NHKのラジオ放送劇『鐘の鳴る丘』に出演することに。良仁たちが演じるのは、当時、社会問題となっていた戦後浮浪児の役。戦争への負い目を胸に抱えた大人たちと共に、伝説となるラジオドラマ『鐘の鳴る丘』をつくる日々が始まる。
戦後の混乱期、ラジオが唯一の娯楽ともいえた時代、作り手側に立つことになった子どもたちが見た世界とは。戦争への後悔を抱えた大人達と一緒に希望を模索する日々の行方は・・・。
【編集担当からのおすすめ情報】
ラジオドラマ『鐘の鳴る丘』は、「緑の丘の赤い屋根 とんがり帽子の時計台 鐘が鳴ります キンコンカン……」の歌と共に語り継がれています。この歌を作曲した古関裕而さんがモデルとなったNHKの朝の連続テレビ小説『エール』では、『鐘の鳴る丘』の制作に至る菊井と小関の物語も登場しました。本書は、この番組に出演した子どもたちの目線から描いた物語です。
良仁や祐介たちは、役を演じるためにと本当の浮浪児を見に行き、大きなショックを受けます。戦災孤児の施設を訪問したときには、施設の子どもから厳しい言葉を投げられ、震災孤児のつらい現実を知ります。それでも、未来を信じて生き抜く子どもたち。大人達が巻き起こす戦争の一番の被害者は、常に、何も知らない子供たちなのです。
同じ地球上で、戦火に怯え、逃れ、苦しんでいる人々がいる今だからこそ『鐘の鳴る丘』の時代を生きた人々の生き様は心に迫ってきます。
同日に発売する著者の『百年の子』という作品には、この昭和の時代から令和の現代までの子供たちの文化や母親の思いと葛藤、親子の絆などが壮大なスケールで描かれています。著者が「一番書きたかったテーマ」と渾身の思いを込めて書き下ろしで執筆したこの作品も、是非一緒に読んでみることをお薦めします。
内容説明
物語は高度成長期の昭和48年、伝説のラジオドラマ『鐘の鳴る丘』に出演した当時小学生の一人、良仁への一本の電話から始まる。それは『鐘の鳴る丘』の脚本家・菊井一夫の葬儀を知らせる電話だった。菊井との記憶に思いを馳せる良仁の脳裏には、主題歌「とんがり帽子」が流れていた。昭和22年、ほとんどの子供がいつもお腹を空かせていた時代。良仁は同じ小学校に通う数名と一緒に、突然『鐘の鳴る丘』に出演することに。それは、戦争への負い目を胸に抱く大人たちと共に、戦争の爪痕と向き合い、未来への希望を模索する日々であった。心に残る名作、待望の文庫化。
著者等紹介
古内一絵[フルウチカズエ]
東京都生まれ。『銀色のマーメイド』で第五回ポプラ社小説大賞特別賞を受賞し2011年にデビュー。17年、『フラダン』が第63回青少年読書感想文全国コンクール課題図書に選出。第6回JBBY賞(文学作品部門)受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
niisun
エドワード
リュウジ
シナモン
はなちゃん
-
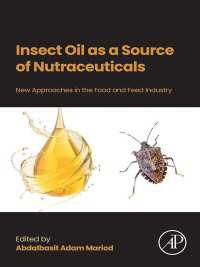
- 洋書電子書籍
- Insect Oil as a Sou…
-
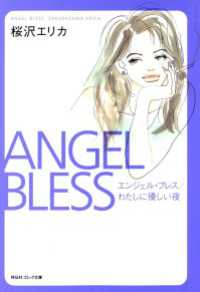
- 電子書籍
- エンジェル・ブレス/わたしに優しい夜 …