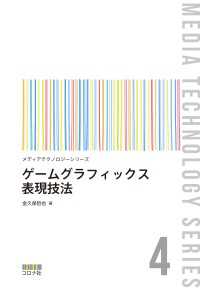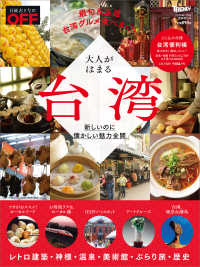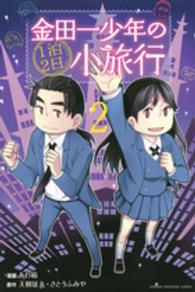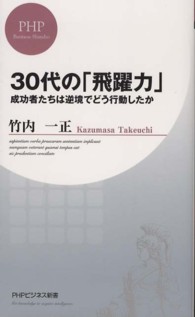出版社内容情報
「まちぐるみ」の子育てで大人も変わる
「まちの保育園」は、東京にある認可保育所。小竹向原、六本木、吉祥寺という異なる街で、特色ある保育を行っています。
例えば・・・毎日の活動を子ども自身が話し合って決める。
運動会やお遊戯会がない。
「コミュニティコーディネーター」なる専任職員がいる。
園に人気のカフェやスタンドがある。
園の理念に、「3つの力を信じる」があります。
●子どもの可能性を信じる
子どもの無限の可能性を信じて、その興味・関心、子どもが「心を動かされる」ことに寄り添う。
●対話の力を信じる
子ども・保育士・保護者・地域の人も含めた、あらゆる関係において対話を重視する。時間確保のため、大人主導の運動会や発表会は行わない。
●コミュニティの力を信じる
地域に開かれた園にする。多様な人とのかかわりによって、子どもの個性や可能性が引き出される。隣近所がつながることで、「孤育て」に陥りがちな家庭や、高齢者や独居老人も新たな交流の機会を持てる。
「まちぐるみ」で子育てをし、子どもたちと「まちづくり」をすることで、より豊かなまちにしていく――これからの保育園のカタチを考えよう。
【編集担当からのおすすめ情報】
「人格形成期」と言われる0?6歳の子どもたち。その間の「出会い」や「経験」の多様性、「学ぶ経験」が、学力だけでなく「やる気」「忍耐力」「協調性」などの非認知的能力を高めることがわかってきました。
そのため、世界的に就学前教育に注目が集まっています。
しかし日本では、待機児童や建設反対などネガティブな話題ばかりが注目され、保育園に代表されるこの時期の保育・教育のグランドデザインが描けていないのではないかーー著者が代表をつとめる「まちの保育園」では、「働く親が子供を預ける」場所としてだけでなく、「まちのインフラ」を目指して、これからの保育園のカタチを模索しています。
子どもにとって理想的な社会は、きっと誰にとっても理想的な社会のはず。
これからの日本社会の在り方についても考えるきっかけになる本だと思います。子育て世代だけでなく、幅広い層のかたに、ぜひ読んでいただきたいと思います。
松本 理寿輝[マツモト リズキ]
内容説明
子どもにとって理想的な環境は、きっと誰にとっても理想的な社会。「まちぐるみ」で子育てを子どもたちと「まちづくり」をこれからの保育園のカタチを考えよう。
目次
第1章 「枠を超えた」保育園をつくりたい(ある子との出会い;保育園と幼稚園の違いも知らなかった ほか)
第2章 子どもが自分で「決める」園(“遊び込む”ためのタイムテーブル;“見せる”運動会やお遊戯会がないわけ ほか)
第3章 一緒に「まち」をつくっていこう(そのまちならではの形;地域と出会うということ ほか)
第4章 社会を「拓く」場所になる(二〇二〇年、日本の学習が変わる;六歳までに身に付く大切なもの ほか)
著者等紹介
松本理寿輝[マツモトリズキ]
ナチュラルスマイルジャパン株式会社代表取締役。1980年東京都生まれ。一橋大学商学部商学科卒業。2003年博報堂に入社。不動産ベンチャーを経て、かねてから温めていた保育の構想の実現のため、10年ナチュラルスマイルジャパン株式会社を設立。東京都認証保育所(のちに認可)「まちの保育園 小竹向原」を設立。現在、六本木、吉祥寺で認可保育所を運営(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mariya926
kao
umico
ぺーはーせぶん
ak