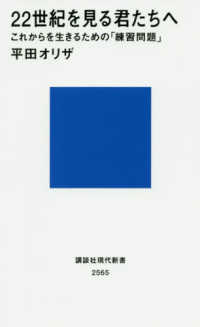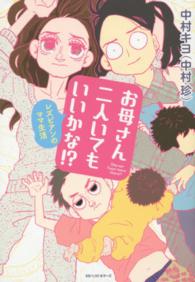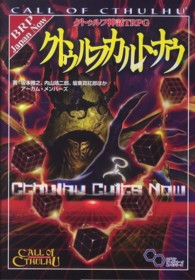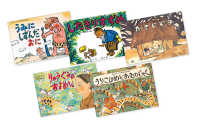出版社内容情報
20世紀、「国語」をめぐって国が行おうとしてきたこと、文学者や知識人が求めてきたこと、庶民がそれらをどのように見つめてきたかを詳細に描き、古書肆「日本書房」の西秋松男氏の証言とともに浮き彫りにする。
明治33年(1900)に国語調査会が発足し、平成12年(2000)に国語審議会が廃止されるまでの100年の間、「国語」をめぐって国が行おうとしてきたこと、文学者や知識人が求めてきたことなどを詳細に描き、古書肆「日本書房」の西秋松男氏の証言とともに浮き彫りにする。明治35年に国語調査委員会が示した基本方針「文字ハ音韻文字ヲ採用スルコトゝシ」に国語施策が長い間縛られ、「当用漢字表」など戦後の諸施策はいわばその集大成であったことが明らかになる。しかし、その後「常用漢字表」の前文で初めて「漢字仮名交り文」が公認されるに至った経緯が述べられ、国語審議会が最後にまとめた「表外漢字字体表」がはらむ諸問題についても具体的に検証する。
内容説明
明治33年(1900)に国語調査会が発足し、平成12年(2000)に国語審議会が廃止されるまでの100年の間、「国語」をめぐって国が行おうとしてきたこと、文学者や知識人が求めてきたこと、そして、それらを庶民がどのように見つめてきたかを詳細に描き、古書肆「日本書房」の西秋松男氏の証言とともに浮き彫りにする。また、国語審議会が最後にまとめた「表外漢字字体表」がはらむ諸問題についても具体的に検証。
目次
第1部 “国語審議会”の歩んできた道(「国語一〇〇年」の淵源;「国語一〇〇年」の前半期;「国語一〇〇年」の後半初期一〇年;「国語一〇〇年」の後半転換期;「国語一〇〇年」の現在;国語審議会と国立国語研究所;中央省庁再編を機に―文化審議会と再新生国語課及び新生国立国語研究所について)
第2部 “漢字仮名交り文”への道のり(明治・大正篇;昭和前期(戦前)篇
昭和後期(戦後)篇)
著者等紹介
倉島長正[クラシマナガマサ]
昭和10年(1935)長野県生まれ。早稲田大学文学部国文科卒
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。