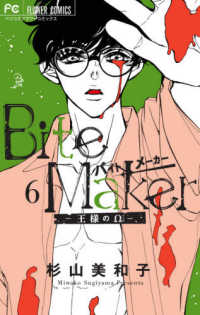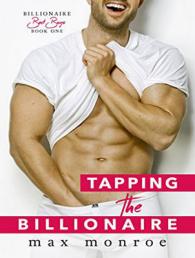出版社内容情報
古代文学の権威であるとともに古代日本海文化の研究に勤しむ著者が、全国約100か所の遺跡と発掘された遺物を手がかりに、万葉歌に隠された縄文エコーを探り出し、一つ一つ解き明かしていくスリル溢れる書。
「沼名河の底なる玉」とうたわれる万葉集の「底なる玉」とは何か。糸魚川のヒスイなのか。だとすると、なぜ縄文人はヒスイでなくてはならなかったのだろう。著者はヒスイに込められた不老不死の精神の流れを説く。「天橋も長くもがも」とうたわれた天橋は縄文遺跡の巨大木柱をいうのか。万葉歌では、不老不死の薬を月に求めて、この歌をうたう。「鳥総(とぶさ)立て舟木伐る」とはどういうことか。ふさふさした葉を付けた梢を立てて、木を伐ることをいうのか。このようにして、樹木に敬虔な縄文人は、伐採にも神への感謝を忘れなかったのであろう。こうして見てくると、海彼(かいひ)の波に洗われた縄文文化が、奈良時代まで継承され、『万葉集』の歌に影を落としているではないか。全国にわたる約100か所の遺跡と、そこから出土した貴重な遺物を手がかりに、著者は大胆な縄文時代の仮説を展開させる。道すじは日本海を越え、大陸へと広がる。朝鮮半島から中国、ロシア、モンゴルへ。このことは、縄文人の先祖や文化が、はるか遠くの大陸からやって来たことを証明する。縄文時代ブームの今、新しい視点で縄文期の真の姿を読みとることができる衝撃の書である。
内容説明
定説をくつがえす縄文謎解きの旅がいま、始まる。
目次
プロローグ 架空ドライブ 日本海側を行く
第1章 沼名河の底なる玉
第2章 天橋も長くもがも
第3章 縄文石に描かれた神話
第4章 鳥スタイルの神々
第5章 弥彦の神の麓の鹿
第6章 縄文の音楽
第7章 鳥総立て船木伐る
第8章 斎瓮を斎ひ掘り据ゑ
感想・レビュー
-

- 電子書籍
- 推しが私を離してくれない!~後輩はVT…