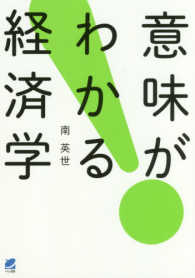出版社内容情報
人間へのひたむきな愛と希望をうたいあげる倉本 聰の作品世界の底には、作者自身の亡き母への挽歌が流れており、その旋律は1975年の「前略おふくろ様」をはじめ、「北の国から」のシリーズにも色濃く流れている。
倉本 聰は、向田邦子、山田太一と並んで、テレビメディアが生んだ今日の最もすぐれたドラマ作家の一人として広く知られている。この三人に共通していることは、テレビドラマの脚本をシナリオ文学の域へとひきあげた作家たちだということである。倉本作品を総覧してゆくと、人間へのひたむきな愛と希望をうたいあげる倉本の作品世界の底には、作者自身の亡き母への挽歌、《母への哀歌》が流れていることに気付く。それは昭和50年から52年にかけて放送されたシリーズドラマ「前略おふくろ様」(全42回)自体の主題が「母」であり、これは昭和56年のシリーズ「北の国から」(全24回)に受けつがれ、以後十余年にわたって連作され今日に及んでいる。都会を離れて北海道の自然のなかで生きる父子の絆を描いた現代家族の叙事詩であるが、妻(母)と別れ、死別される主人公家族にとって、もう一つの《母の哀歌》であり、母なるものへの終わらない旅なのである。著者は、倉本作品にひそむ《母の哀歌》に着目し、ドラマのもつ清々しい人間賛歌と、その感動の秘密を解きあかしてゆく。十余年にわたる固定された出演者の成長や老いは人生そのものであり、視聴者・読者の人生とダブってくる
目次
1 母への哀歌(板前サブの修業時代―「前略おふくろ様」;続・板前サブの修業時代―「前略おふくろ様」 ほか)
2 見捨てられた子供たち(倉本聡氏とNHKとの不幸な関係―倉本聡のドラマトゥルギー;母よ、淡くかなしきもののふるなり―「りんりんと」の母と子;老いの哀しみ―「幻の町」流離譚)
3 「北の国から」の愛(家族の肖像;「北の国から」の自然と人間 ほか)