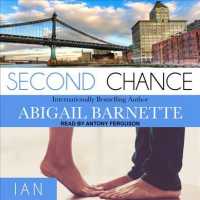出版社内容情報
井沢 元彦[イザワ モトヒコ]
著・文・その他
内容説明
幕府を崩壊させた“一発の銃弾”。密勅、大獄、桜田門…激情の幕末史全真相。
目次
第1章 幕末激動の十五年 一八五八年編―戊午の密勅と安政の大獄(水戸黄門の隠居所・西山荘から生まれた「倒幕正当化の思想」;“血”を見ずに事を収めようとした老中・堀田正睦の「判断ミス」 ほか)
第2章 幕末激動の十五年 一八五九年編―正論の開国VS実行不可能な攘夷(“行動の人”吉田松陰が門下生に発した「草莽崛起」という思想;「倒幕」が論理的に正当化されることになった「一君万民論」 ほか)
第3章 幕末激動の十五年 一八六〇・六一年編―桜田門外の変大老暗殺が歴史を変えた!(井伊直弼をして大弾圧に走らせた「水戸の大陰謀」という事実誤認;島津久光に藩内過激派を押さえ込ませた大久保一蔵の「絵図」 ほか)
第4章 特別編(言霊信仰と安全神話の崩壊 巨大災害と日本人;今こそ、織田信長の「突破力」に学べ!「四分の一国主」から天下人に登りつめた男の軌跡)
著者等紹介
井沢元彦[イザワモトヒコ]
作家。1954年2月、愛知県名古屋市生まれ。早稲田大学法学部卒業。TBS報道局記者時代の80年に、『猿丸幻視行』で第26回江戸川乱歩賞を受賞。現在は執筆活動に専念し、独自の歴史観で『逆説の日本史』を『週刊ポスト』にて好評連載中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ひろき@巨人の肩
81
幕末の裏キーマン、井伊直弼と孝明天皇にスポットを当てた本巻。井伊直弼は、清国のアヘン戦争敗北を見て日本救国の為、開国派として日米通商条約を調印し日本の近代化を断行。13代家定の将軍継嗣問題でも南紀派として、一橋派の島津成彬、松平慶永らが擁立する慶喜を抑え、家茂を擁立。そして反対者達の粛正として安政の大獄を敢行。一方、攘夷論者の孝明天皇は、欧米列強との通商条約に勅許を与えず。水戸藩への幕府改革を指示する戊午の密勅が下賜され、開国派と尊皇攘夷派の対立が激化。桜田門外の変での井伊直弼暗殺へと繋がる。2024/10/20
ころこ
38
井伊直弼が魅力的だ。ロベスピエールを直ぐに思い浮かべたが、言及されている。魅力的な理由は肯定、否定の両面でみることができるからだ。この人物を両面でみることが出来るということが、モノの見方に奥行きをつくることであり、歴史学の、人文学の意義のひとつであるはずだ。彼は全共闘世代の革命戦士に似ている。悲しくも似ている似姿をみなければ、歴史の教訓は得られない。外国との条約交渉でオランダが登場する。オランダは江戸時代の唯一の友好国だが、この時の条約交渉を英米に比べて軽視したことが、後の「外交の敗北」に繋がっていると指2022/10/24
RASCAL
19
大老・井伊直弼は、実は意外と聡明な人だったのではないかと思いながら読んだのですが、やはり体制内の門閥でした。名門のエリートってのはろくなことをしない。安政の大獄も、開国のためというよりも、一橋派を追い落とす権力抗争で、その結果の桜田門外の変ということか。小栗上野介や勝海舟とは全然器が違う。徳川幕府、ここでルビコン川を越えちゃったかな、ということで次巻にいきます。 2016/03/16
よっしー
16
本シリーズでは、幕末から明治維新までが非常に丁寧に書かれている。やはり日本史を語る上で重要な時期ということだろう。外国との接近は特に孝明天皇にとって穢れを避けるという宗教的な意味合いが強かったが、実際にコレラが入ってきたことは事実のようなので、科学的にも日本に大きな影響を与えている。印象的だったのは民主化について。西洋においては神が絶対的な存在であるために神の下での平等が実現し、日本においては絶対的存在である天皇の下での平等が民主主義を確立したとのこと。今まで考えたことのない興味深い論点だった。2024/12/15
すきま風
16
歴史好きに薦められて。天璋院、和宮、島津斉彬、家茂、西郷、勝…好きなところなので読むのが楽しかった。篤姫にはまってから色々な本を読みあさっていたけど、また新たな解釈が読めて面白い。続きもぜひ読んでみよう。2016/09/08