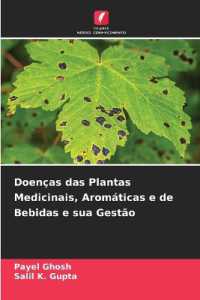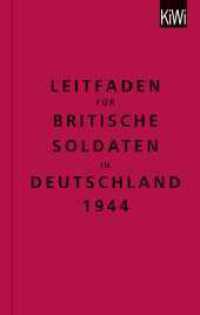出版社内容情報
徳川幕府による厳しい身分制度下、権力の重圧にあえぐ者たち。多彩な人物群と雄大な構想、透徹した歴史観で綴る白土劇画の代表作であるばかりでなく、日本コミック史上に燦然と輝く名作。
▼第1章・誕生▼第2章・カガリ▼第3章・剣▼第4章・マスドリ●主な登場人物/カムイ(差別の壁を力で乗り越えようとする夙谷の少年)、正助(才覚溢れる貧しい農民の子)、草加竜之進(次席家老のひとり息子)●あらすじ/幕府による厳しい身分制度がしかれていた江戸時代。その寛永年間(1624?1634年)末の日置藩七万石領内。厳しい差別を受けていた人々の集落は、夙谷(しゅくだに)という地域にあった。その夙谷に生まれたカムイは、このような社会の中で“生きる誇りと自由”を得るためには、自分が強くなる以外に方法はないという信念を持つ。そんなカムイがふとしたことで知り合いとなった少年の正助。貧しい農民の子として生まれた彼も、カムイほどではないにしても恵まれない境遇にあったが、いつかは現在の境遇から抜け出して自分の家や田が持てる立場になりたいと願っていた。ある日、カムイの母親が重い病にかかるが、夙谷の病人ということで町の医者から診察を拒否される。自分の母親が、ろくな手当ても受けずに死んでしまったことで、言いようのない怒りを感じたカムイは、その怒りを森で出会ったイノシシと戦うことで晴らそうとする。しかし、逆にカムイは傷ついて意識を失
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ぶち
72
(再読) 再読といっても30年振り。最初に読んだのは小中学生の頃です。30年振りに読んでみて、厳しい身分制度に縛られた封建社会における過酷な搾取の時代をどうにかして生き抜いてゆこうという下層の人々の生き様が、小中学生の頃に感じたよりも数倍も心を打ちます。 漫画の代表的な古典名作だと認識をあらたにしました。 第一作では主人公のカムイの登場は少ないのですが、最下層の非人であっても超然としていて、幼い頃からヒーローの風格を備えていたことが分かり、今後どう活躍していくのか、おおいに期待します。2024/08/06
いちろ(1969aMAN改め)
12
父の友人が下さった、文庫版全集が実家にある。ははーん、忍者漫画だね、読むもの切らしたし、ちょっと。手に取ってビックリ。江戸の庶民、しかも非人といわれる百姓以下の人間たちを主人公に物語は進む。カムイはむしろ象徴的な、あるいは何かなのか。今6巻を読んでいる。まだまだ先があり、日に一冊ずつ進む感じ。なんとなく差別はいかん!程度で育ってきた自分には強烈すぎ、学ぶものが多い。大変な読み物に出会ってしまった感がある。2014/10/24
白義
12
正直、古い大河漫画ということで今から読むとそこまででも、と最初は思っていたが、オオカミたちを通して描かれる、流転するサイクルをそのまま写したかのような自然の広大さにしびれ一気読み。一コマ一コマに異常な情報量が詰め込まれた一種の全体漫画で、封建社会の過酷な差別体系もそのまま自然のうちに含まれ、それに立ち向かう人々の生命力がさらに輝きを増しているように思う。これでもこの後広がっていく群像劇の序章に過ぎないのだから、なるほど確かに大変な作品だ2014/06/25
いずみんご
10
農民を支配するために作られた庄屋、百姓、下人、非人の身分制度。人に非ずと書くように、非人は犬並みの扱いであることや、犬を的にして流鏑馬の練習をする武士、白い狼の話など、もう胸が痛い描写ばかり。ふだん時代小説を読むことが多いけれど、こうした面は知らなかっただけに、物語の裏側を知るようで興味深かった。江戸はこうして成り立っていたんだなあ。差別が、当初は自分たちの身を守るために生まれたことも、白い狼のエピソードからも知りました。とはいえ、人間社会でそれを正当化してはいけないけれども。次巻に続く。2022/01/24
猫丸
10
とにかく絵がうまい。オオカミの疾走、イタチが動きを止めた瞬間、横一文字に払った刀の軌跡。小さな文庫版で見ても美しい。物語は封建制安定期の地方藩で始まる。支配階級は悪の限りを尽くし、本百姓たちは上から支配され下人・非人を差別する状況。カムイは最下層身分から登場する。人間は自然を所与とみなし、支配者は下層民を所与とみなす世界。悪辣な顔で描かれる武士階級だが、彼らに悪であらんとする意識はないのだろう。社会変革の方向と可能性を探っていた1960年代の作品を再読することに。2021/10/17