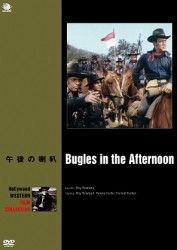出版社内容情報
恐怖が生まれ増殖する場所は、いつも「学校」だった――。
繰り返しながら進化する「学校の怪談」をめぐる論考集。
90年代にシリーズの刊行が始まり、一躍ベストセラーとなった『学校の怪談』。
コミカライズやアニメ化、映画化を経て、無数の学校の怪談が社会へと広がっていった。
ブームから30年、その血脈は日本のホラーシーンにどのように受け継がれているのか。
学校は、子どもたちは、今どのように語りの場を形成しているのか。
教育学、民俗学、漫画、文芸……あらゆる視点から「学校の怪談」を再照射する一冊。
目次
1章 「学校の怪談」はどこから来て、どこへ向かうのか ―― 一柳廣孝
2章 「学校の怪談」と戦争の影 ―― 吉田悠軌
3章 「学校の怪談」ブームのさきがけ
ホラー雑誌と怪談投稿文化 ―― 廣田龍平
4章 令和によみがえる『地獄先生ぬ~べ~』 ―― 真倉翔 岡野剛
5章 「大学怪談」の世界 ―― 吉田悠軌
6章 「学校の怪談」を調査する ―― 朝里樹
7章 特別寄稿 “つなぐ”学校の怪談 ―― 吉岡一志
8章 ブックガイド 現代ホラー小説は学校怪談をどう描いてきたか ―― 朝宮運河
【目次】
目次
1章 「学校の怪談」はどこから来て、どこへ向かうのか
2章 「学校の怪談」と戦争の影
3章 「学校の怪談」ブームのさきがけ ホラー雑誌と怪談投稿文化
4章 令和によみがえる『地獄先生ぬ~べ~』
5章 「大学怪談」の世界
6章 「学校の怪談」を調査する
7章 特別寄稿 “つなぐ”学校の怪談
8章 ブックガイド 現代ホラー小説は学校怪談をどう描いてきたか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
XX
おおかみ
まさ☆( ^ω^ )♬
いりあ
-

- 電子書籍
- ダメ貴族になりたい公爵令嬢【タテヨミ】…
-
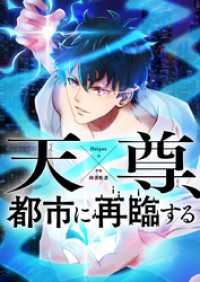
- 電子書籍
- 天尊、都市に再臨する【タテヨミ】第14…
-
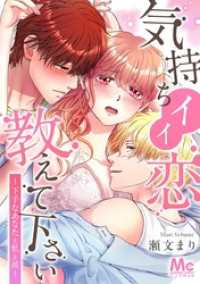
- 電子書籍
- 気持ちイイ恋 教えて下さい~下手なあな…
-

- 電子書籍
- 大人の名古屋vol.38 『特集 名古…