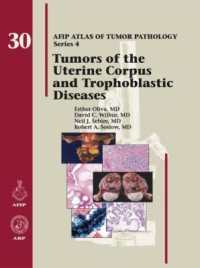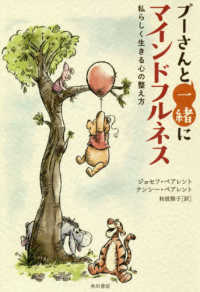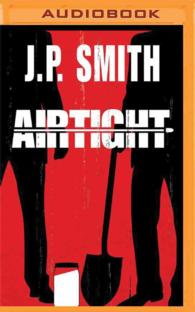出版社内容情報
第14回開高健ノンフィクション賞受賞作。中米ホンジュラス、世界一凶悪と言われる若者ギャング団「マラス」に身を投じる少年たちと彼らを救おうとする人々の姿を追った衝撃のルポルタージュ!
工藤 律子[クドウリツコ]
内容説明
殺人事件発生率世界一の中米ホンジュラスにはびこる凶悪な若者ギャング団、「マラス」を取材した衝撃のルポルタージュ!2016年第14回開高健ノンフィクション賞受賞。
目次
第1章 マラスの輪郭
第2章 カリスマ
第3章 マラスという敵
第4章 冒険少年
第5章 マラスの悲しみ
第6章 変革
著者等紹介
工藤律子[クドウリツコ]
1963年大阪生まれ。ジャーナリスト。東京外国語大学大学院地域研究研究科修士課程在籍中より、メキシコの貧困層の生活改善運動を研究し、フリーのジャーナリストとして取材活動を始める。主なフィールドはスペイン語圏、フィリピン。NGO「ストリートチルドレンを考える会」共同代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
starbro
127
3月の1作目は、開高健ノンフィクション賞受賞作『マラス』です。書店で見掛けて、図書館に予約したので、ようやく読めました。極貧から派生する暴力、犯罪、負の連鎖、日本とは全く違う状況です。かなり危機的な状況でありながら、本書を読んでいてあまり戦慄を覚えないのは、ラテンの国だからでしょうか?それとも著者がマラスを温かい眼で見ているからでしょうか?本書では救いが見える状況で若干安心出来ますが、トランプ米大統領がメキシコ国境に壁を築き、不法移民対策を徹底的に行う場合には、もっと悲惨な状況が待っていると思われます。2017/03/01
ナミのママ
56
第14回開高健ノンフィクション賞受賞作。メキシコの南にある国「ホンジュラス」は殺人事件発生が世界一だという。そこの若者ギャング団を「マラス」というらしい。この本は「マラス」を追ったルポでした。プロローグで「なぜマラスを取材するようになったか」が延々と続きます。さらに第一章ではマラスの説明が延々と続き、正直、このあたりで読むのを止めようかと思いました。しかし取材部分になると、国の情勢、環境、宗教そのあたりがわからないとこれは理解できない内容だと気がつきます。エピローグの内容までしっかりしていて良かったです。2017/01/07
キク
50
開高健賞受賞作。中米のギャング「マラス」について26年間取材を続け、NGO「ストリートチルドレンを考える会」を創設した女性によるノンフィクション。「スラム街から抜け出すには、ラッパーかバスケで成功するしかない」といわれてるけれど、中米ホンジュラスの若者は「マラスに入るか、移民にならなければ生き残れない」という状況に追い込まれている。移民を希望する人々を支援する「移民の宿」は、生きるためには移民が必要だと考えるカトリック教会が運営している。その通りだ。死なないためには生き残るしかない、彼らも、そして僕たちも2021/12/28
TATA
49
殺人、麻薬ギャング団があまりにも日常にある中米諸国。世界一の殺人事件発生率の地、その厳しい環境の中では学校に行くことさえままならず、ギャングに身を投じるしかない少年たち。この作品はその救済に当たる元ギャングの神父たちを追うルポルタージュ。行き場のない少年たちだけれども、この国の紐帯は宗教によってもたらされる。読後、今の日本をどう感じるのか、渾身の作品ですね。開高健ノンフィクション賞受賞作。2019/07/08
ばんだねいっぺい
39
マラス=中米のギャングの総称。都市部中心にはびこり、貧困層の若者たちは、仲間になるか、餌食になるか、逃げ続けるかの選択を強いられる。マチスモの価値観もあり、ギャング加入には、金銭や組織の威光から来るリスペクトを得られるために抗しがたい魔的な誘因力がある。こういう中間暴力こそが生活に最も近く、この本では、マラスの若者たちにスポットが当たっていたが、地元生活者の大人たちの生の実感や、富裕層の視線や見方、政府のこれからの施策の行方も知りたくなった。興味が尽きない一冊。2019/02/19
-
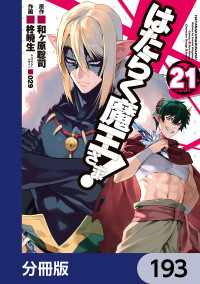
- 電子書籍
- はたらく魔王さま!【分冊版】 193 …