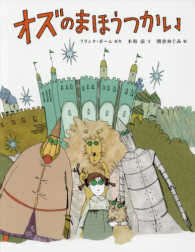内容説明
白鳳期の歌(第一・二期)を前半に、奈良朝の歌(第三・四期)を後半に配列した「古今構造」の歌巻である巻三と巻四とを収録。三大部立の他に大伴家持の創案によると思われる「譬喩歌」の部立が新たに加わる。奈良朝初期の宮廷歌人、山部赤人・高市黒人たちが活躍し、旅人・家持・坂上郎女ら大伴一族の作品も初登場する。「相聞」歌集巻四には、天平の若き貴公子大伴家持をめぐる女性たちの恋歌が多いのも特色。
目次
万葉集巻第三(雑歌;譬喩歌;挽歌)
万葉集巻第四(相聞)
著者等紹介
伊藤博[イトウハク]
1925~2003。長野県生まれ。1952年、京都大学文学部卒業。文学博士。筑波大学教授、共立女子大学教授などを歴任。万葉学会代表を務めた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
崩紫サロメ
12
第3巻・4巻を扱う。前巻に続き、「歌群」として捉える。3巻雑歌の部、「あおによし奈良の都の咲く花の」は太宰府での歌だったのか、とかそれを結ぶ形で山上憶良の「憶良らは」歌があるのか、など。個人的には338からの大伴旅人の酒讃歌13首、日本では珍しいジャンルでながら、中国の飲酒詩に匹敵する構えがあるという評価には同感。また、この13首が旅人個人の文学遺産であると同時に、太宰府歌壇の共有財産であり、個に即する近代文学の次元に立って鑑賞することの危険性への指摘、その通りだと思った。2021/01/29
KAZOO
3
2巻目ですが、この萬葉集の文庫本は本当に従来のものに比べて読みやすいといつも思っています。文字も大きくてわかりやすい解説です。2013/04/11
月音
2
『新古今和歌集』『百人一首』でおなじみ、「田子の浦~」の歌が載る。新古今時代と万葉時代の田子の浦は、場所が違うらしい。最初から全景が見えている富士と、ゆっくりと歩みつつ山影から徐々に姿を現す富士。同じ「うち出でて」でも、感動の質は違う。山上憶良が宴席で、「もう帰るわ。家で赤ん坊泣いてるし、母ちゃんも待ってるからー」という意の歌を詠んでいるのに笑う。しかし、憶良はこのとき七十一歳。家に彼の帰りを待つ人はいない。場がどっと沸いた後の空気に混じる、一滴の寂寥感。⇒続2024/05/19