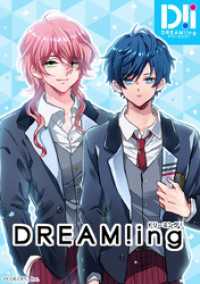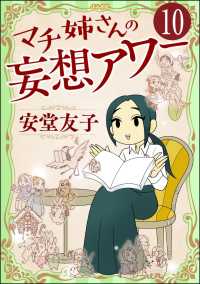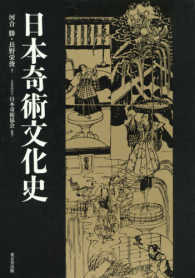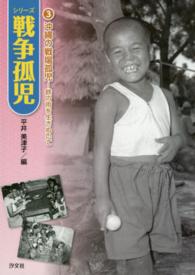内容説明
「本書の主人公は発見者としての人間である」誰が、いつ、どのようにして、それまで知られてなかった知識を人類にもたらしたか?最初の大発見は「時間」であった。月を区切り、週を分け、年を数え、一日の時間・分・秒を定めることを通して、人類は時間を発見していく…現代アメリカを代表する知性であるピューリッツァー賞受賞学者が、エキサイティングに描く、未知に挑んだ人類の歴史。
目次
第1部 時間(天上の帝国;太陽の時間から時計の時間へ;伝道師の時計)
第2部 陸地と海洋(想像の地理学;東方への道)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
99
この本は以前にも分厚い1冊本で読んでいるのですが、それが見つからず文庫本で登録していました。今回も同じなのでそれぞれ4冊に分かれた文庫本に感想を書いていきます。1冊目は第一部の「時間」ということで暦や時計の歴史を繙いてくれています。ナイルの水位が暦を作った、ということから1週間がなぜ7日になったのか、あるいはガリレオ・ガリレイの登場した意味などが説明されています。私にとっては好奇心を満たしてくれる愉しい本です。2025/08/20
あーさん☆来年も!断捨離!約8000冊をメルカリでちびちび売り出し中!(`・ω・´)ゞ
29
高校で読んだ本。
白義
14
アメリカを代表する歴史家が描く、西洋を中心にした人類の発見に関しての一大百科全書的歴史書。世界史の面白さを知るなら未だに最高レベルの本じゃあないか。その文庫分冊の、一巻目。一巻の主題は時間と空間で、暦、時計の誕生や想像の地理学から東西交流がメイン。細かな歴史の事実と、それが人類史に与えた世界観上の衝撃をバランスよく描いていて面白い。ただし、時計の話がメインで人間があまり出ない一部は退屈かも。本番は二部、陸地と海洋から。十字軍や東方見聞録といったものが空間の拡大という視点から語られている2012/02/24
磁石
13
「時間」についての各時代・各地域の考え方一覧、がほとんどではあるものの、改めて指摘されると不思議を感じさせられる。それまで時間というものは、日時計・水時計・蝋時計などのように一度流れたら二度と戻らないあり方をしていた。でも、機械時計の発明によりそれは変わった。時間は回転で繰り返されるもので、誰でも持ち運び可能なものとなった。それがなぜ西洋文明で発明されたのか、なぜそれ以外の場所では生まれなかったのか、腕時計の謎。……魅力的だけど疑問の提示に終わって、それを深く掘り下げてくれなかったのは残念。2015/01/31
彬
9
「時間」と「地球上の地理」について扱っている。時間の章では月の満ち欠けから我々の知る秒に至るまでのあらましが語られ、地理では古代人が計算や経験によって驚くべき計測を行い、それが中世に入って廃れ持ち直すまでを扱っている。時間の概念は面白いもので、当たり前に使っているものがその実、新しい発見であるのは妙な驚きを覚えた。なかなか昼夜の区別から進めなかったのは夜が明るい現代では分からない感覚だ。地理にでは古代の計測は既知だったが中世西洋で想像で地図が描かれていたのは知らなかった。伝道が再発見に繋がるのは皮肉である2013/07/21