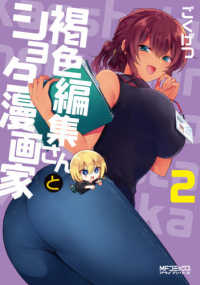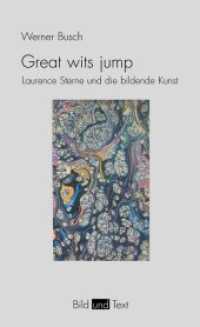出版社内容情報
大正生まれの小川万亀は、山梨の裕福なお菓子屋の末娘。優秀な彼女は東京の女学校に進む。現実の壁に幾度もくじけながら、常に前向きに夢を持ちつづけた女性の激動の半生の物語。(解説/中島京子)
内容説明
山梨の裕福な菓子商の末っ子として生まれた万亀は児童文芸誌「赤い鳥」を愛読する少女だった。勉強がよく出来た万亀は、女専に進み東京の華やかな生活を知るも、相馬に行き教師となるのだが―。進学、就職、結婚のたびに幾度も厳しい現実の波に翻弄されながらも、いつも彼女のそばには大好きな本があった。大正から昭和にかけての激動の時代、常に前向きに夢を持ち続けたひとりの女性の物語。
著者等紹介
林真理子[ハヤシマリコ]
1954年山梨県生まれ。日本大学芸術学部卒。82年エッセイ集『ルンルンを買っておうちに帰ろう』でデビュー。84年処女小説『星影のステラ』が直木賞候補作に。86年「最終便に間に合えば」「京都まで」で第94回直木賞を受賞。95年『白蓮れんれん』で第8回柴田錬三郎賞を、98年『みんなの秘密』で第32回吉川英治文学賞を、2013年『アスクレピオスの愛人』で第20回島清恋愛文学賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
夜長月🌙新潮部
86
林真理子さんの母上の半生です。大正4年に産まれてから真理子さんを産む数年前までのお話し。各章のタイトルに「大地」など書籍の名が使われているのも素敵です。母上の人生には読書が深く関わっていたことがわかります。そしてこの本ではその時代背景にも関わらず女性でありながら一個人として生きた証が赤裸々に綴られています。本を読むこと、勉強をすることが女性としてさげすまされるような時代があったことを忘れてはなりません。とても凛々しい生き方だと思います。2020/05/24
naoっぴ
79
【女祭り2@月イチ】林真理子さんの母親がモデルの、大正~昭和初期を過ごした女性の物語。林さんはエッセイは読んだことはありますが、これほど読みごたえある小説を書かれる人だったのかと驚きました。小さい頃から本に触れ色々な生き方を知っていたであろう万亀は、気骨も自立心もありながら世間の常識から抜け出すほどの行動力はなく、矛盾を抱えながらも前向きに生きていく。そんな万亀の気持ちに自分を重ねどっぷり感情移入。本とともに繋ぐ人生、最後に辿り着いた居場所もまた。憧れにも似た感動と、本への想いに胸が熱くなりました。2016/05/30
Ikutan
76
大正生まれのお母様をモデルに、希望に満ちた大正から混乱の終戦後まで、時代に翻弄されたひとりの女性の半生を描いた物語。勉強家で成績優秀。大柄で働き者。何より読書を愛する万亀。女性の自己表現が難しかった時代に、自由を求めながらも、どこか諦めも抱えたその人生は同じ女性として思うこと色々。真理子さんの鮮やかな筆致にぐんぐん引き付けられます。時代と共に生きづらくなりながらも、本との接点を失わないその生き方は、本好きとしては嬉しい展開です。確かに林作品の一押しですね。読メのお蔭で、またまた素敵な作品に出会えました。2016/06/24
buchipanda3
71
太宰の「斜陽」繋がりで手に取った。大正に生まれ昭和の激動の時代を生きた一人の女性の半生を描いた長編。モデルは著者の母親とのこと。商家の末娘として育った万亀(まき)は姉たちと比べ器量はないが読書好き。自分は結婚せずに好きに本を読んでいたいと願うも、進学、就職など人生の節目を迎えるごとに現実にぶち当たる。ままならない中でも幸せを追い続ける姿はしんどそうだが、そのタフさに感じ入った。そして「斜陽」が彼女の前に現れる。当時、彼女と同様にかず子の姿が多くの女性を鼓舞したのでは。そして現代はこの本もきっとその役割を。2019/05/23
はる
68
読み応えがありました。本好きな少女が、夢に憧れながらも時代の波に翻弄され、過酷な現実と向かい合って生きていく物語。綺麗事ばかりではなく、妬みや僻みの感情も赤裸々に描いています。決して魅力的ではない主人公ですが、何故か自分と重なる部分がありました。主人公が年を重ねるにつれて、軽蔑していた母親を頼りにしたり、甘えたりするようになっていく感情の変化が生々しいです。母は強し。2015/08/20
-

- 和書
- 企業経営の理論と実態