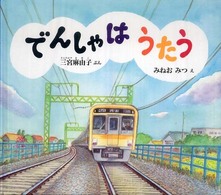出版社内容情報
安倍政権以降、「学力向上」や「愛国」の名の下に政治が教育に介入し始めている。
その結果、教育現場は萎縮し、教育のマニュアル化と公教育の市場化が進んだ。
学校はサービス業化、教員は「使い捨て労働者」と化し、コロナ禍で公教育の民営化も加速した。
日本の教育はこの先どうなってしまうのか? その答えは、米国の歴史にある。
『崩壊するアメリカの公教育』で新自由主義に侵された米国の教育教育「改革」の惨状を告発した著者が、米国に追随する日本の教育政策の誤りを指摘し、あるべき改革の道を提示する!
鈴木大裕(すずき だいゆう)
1973年、神奈川県生まれ。
教育研究者。
16歳で渡米し、1997年コールゲート大学教育学部卒業、
1999年スタンフォ―ド大学教育大学院修了。
帰国後、千葉市の公立中学校で英語教師として勤務。
2008年に再渡米し、コロンビア大学教育大学院博士課程へ。
2016年、高知県土佐町へ移住、
2019年に町議会議員となり、教育を通した町おこしを目指しつつ、執筆や講演活動を行なっている。
著書に『崩壊するアメリカの公教育』(岩波書店)など。
内容説明
安倍政権以降、「学力向上」や「愛国」の名の下に政治が教育に介入し始めている。その結果、教育現場は萎縮し、教育のマニュアル化と公教育の市場化が進んだ。学校はサービス業化、教員は「使い捨て労働者」と化し、コロナ禍で公教育の民営化も加速した。日本の教育はこの先どうなってしまうのか?その答えは、米国の歴史にある。『崩壊するアメリカの公教育』で新自由主義に侵された米国教育「改革」の惨状を告発した著者が、米国に追随する日本の教育政策の誤りを指摘し、あるべき改革の道を提示する!
目次
第1章 「お客様を教育しなければならない」というジレンマ―新自由主義と教育
第2章 人が人でなくなっていく教育現場―教員の働き方改革の矛盾
第3章 新自由主義時代の「富国強兵」教育と公教育の市場化―政治による教育の「不当な支配」
第4章 「自由」の中で不自由な子どもたち―コロナ禍が映し出した教育の闇と光
第5章 「教師というしごとが私を去っていった」―教育現場における「構想」と「実行」の分離
終章 「遊び」のないところから新しい世界は生まれない
著者等紹介
鈴木大裕[スズキダイユウ]
1973年、神奈川県生まれ。教育研究者。一六歳で渡米し、97年コルゲート大学教育学部卒業、99年スタンフォード大学教育大学院修了。帰国後、千葉市の公立中学校で英語教師として勤務。2008年に再渡来し、コロンビア大学教育大学院博士課程で学ぶ。16年、高知県土佐町へ移住、19年に町議会議員となり、教育を通した町おこしを目指しつつ、執筆や講演活動を行なっている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まーくん
あみやけ
Kーazuki
まこみや
たまきら