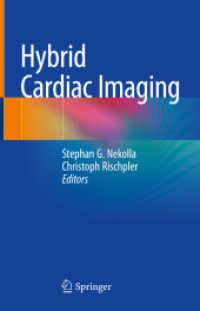出版社内容情報
「文学作品はもういい! 実社会で使われるような文章を読ませるべきだ!」
そんな声に押され、国語教育の大改造が始まった。
文科省が重視したのは実用性。
文学はこの枠には入らないという。
しかし、この考え方は正しいのか?
文章を読む際に大事なのはことばの「形」を見極める力だと著者は言う。
そこを鍛えるトレーニングをしたい。
その助けになるのが文学作品を読む技術なのだ。
本書では契約書、料理本のレシピ、広告、ワクチン接種の注意書き、小説、詩など幅広い実例を用いて「形」を読む方法を指南する。
それは、生成AIが生み出す「文章」と渡り合う際にも格好の助けになるだろう。
画期的な日本語読本の誕生!
【目次】
第1章 学習指導要領を読む
第2章 料理本を読む
第3章 広告を読む
第4章 断片を読む
第5章 注意書きを読む
第6章 挨拶を読む
第7章 契約書を読む(1)
第8章 契約書を読む(2)
第9章 小説を読む
第10章 詩を読む
【著者略歴】
阿部公彦(あべ まさひこ)
1966年生まれ。
東京大学文学部教授。
専門は英米文学。
東京大学大学院修士課程修了、ケンブリッジ大学大学院博士号取得。
訳書に『フランク・オコナー短篇集』(岩波文庫)、共著に『ことばの危機』(集英社新書)、著書に『事務に踊る人々』(講談社)『名作をいじる』(立東舎)『小説的思考のススメ』(東京大学出版会)『英詩のわかり方』(研究社)『病んだ言葉 癒やす言葉 生きる言葉』(青土社)など。
内容説明
「文学作品はもういい!実社会で使われるような文章を読ませるべきだ!」そんな声に押され国語教育の大改造が始まった。文科省が重視したのは実用性。文学はこの枠には入らないという。しかし、この考え方は正しいのか?文章を読む際に大事なのはことばの「形」を見極める力だと著者は言う。そこを鍛えるトレーニングをしたい。その助けになるのが文学作品を読む技術なのだ。本書では契約書、料理本のレシピ、広告、ワクチン接種の注意書き、小説、詩など幅広い実例を用いて「形」を読む方法を指南する。画期的な日本語読本の誕生!
目次
第1章 学習指導要領を読む
第2章 料理本を読む
第3章 広告を読む
第4章 断片を読む
第5章 注意書きを読む
第6章 挨拶を読む
第7章 契約書を読む(1)
第8章 契約書を読む(2)
第9章 小説を読む
第10章 詩を読む
著者等紹介
阿部公彦[アベマサヒコ]
1966年生まれ。東京大学文学部教授。専門は英米文学。東京大学大学院修士課程修了、ケンブリッジ大学大学院博士号取得(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
よっち
いちろく
武井 康則
Танечка (たーにゃ)
-

- DVD
- 戦国BASARA 其の弐