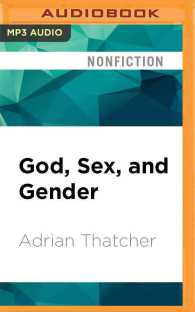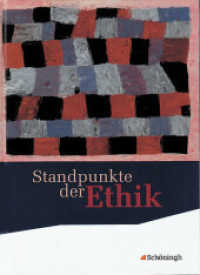出版社内容情報
「共同通信ヘイト問題取材班」の記者が、現場の実態報告とともに報道がどう向き合ってきたかを検証する、ヘイトスピーチ問題入門書。
内容説明
二〇一六年の「ヘイトスピーチ解消法」施行以後、過激なヘイトスピーチデモは減る一方、ネット上での差別発言はいまだ横行している。その背景にいわゆる「官製ヘイト」や歴史修正主義があることは見逃せない。本書は、「共同通信ヘイト問題取材班」としてヘイトスピーチデモの現場で取材を重ねてきた著者が、メディアはそれとどのように向き合ってきたのかを検証。日韓の戦後補償問題を長年追い続けてきた著者だからこそミクロとマクロ両方の視点からの解説が可能となった、「ヘイトスピーチ問題」の入門書である。
目次
第1章 ヘイトスピーチと報道
第2章 ヘイトの現場から
第3章 ネット上のヘイト
第4章 官製ヘイト
第5章 歴史改竄によるヘイト
第6章 ヘイト包囲網
著者等紹介
角南圭祐[スナミケイスケ]
1979年、愛媛県出身。大阪外国語大学卒業。愛媛新聞記者を経て、渡韓しフリージャーナリストに。2009年共同通信入社。大阪社会部、福岡編集部、社会部を経て2020年から広島支局次長。「共同通信ヘイト問題取材班」の一員。日本軍慰安婦や徴用工など日韓の戦後補償問題について長年追い続けている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
61
ヘイトスピーチは表現の自由の範疇には入らない暴力であるという著者の基本姿勢に同意する。その立場から書かれた本書の最終章については政治家諸氏に是非とも真剣に検討していただきたい。いわゆる「差別論」的には物足りなさもあったが、「おわりに」で著者が少年期に「差別主義の右翼少年だった」とカミングアウトする内容で合点がいった。また、政府や一部の首長がヘイトを助長しているという指摘は重要。ただ、「差別と資本主義は親和性が高い」という見解は同意できるものの、「反資本主義」が差別から遠くなるというのは論理の飛躍を感じた。2021/09/11
Masakazu Fujino
17
とてもよい本であるけれど、胸をつかれる本でもある。自らを省みて傍観者になってはいないだろうか?きちんと差別を許さない取り組みができているだろうかと考えさせられた、闘うジャーナリストの書いた良書。 本文より『差別をしない人はいない。誰でも、マイノリティでさえも、差別をしてしまうことがある。無自覚的にも無自覚的にも。「私は差別をしない」という人を私は信じない。「私は差別をしない」では差別はなくならない。「私は差別に反対する。闘う」でなければならない。」2021/07/13
kenitirokikuti
9
ドロンパが政治ゴロなのは否定しないが、カウンターに「過激派」が加入してきてるのも間違いないでしょ。在特が街宣場所を大久保から神奈川県川崎市に移して、っちゅうのに何を感じるかは人それぞれだが、パンピーが関わらん方がいい、でしょ▲新聞労連の事情は、たまに手にする週刊金曜日や選択などの記事で知ることがある。日韓の報道産業廃棄物の労組事情はけっこう複雑と知った。よくアニメファンがどうこう言われたりするが…俳協があるからね…ボイス収録でサービス残業さしたりとか出来ないはず(こちらは終わったときが終わったときだナー2021/07/26
tolucky1962
7
ヘイトスピーチ解消法も表現の自由に委縮。警察が守るヘイトデモはカウンタにより減ったが巧妙で市の判断は困難。野放しネットを開示請求する被害者の負担大で泣き寝入りに。脅せば黙るという差別主義者。調べる術なくブログを信じ書き込む多くはプロでない。理不尽な政府の歴史改竄。国際人権規約で差別禁止の法的義務を負う日本。国が責務を自治体に要請。包括的差別禁止法がない。身分制,植民地が育てた資本主義は差別を生む。違法判断は難しいが名誉棄損罪は線引きしている。法律ができれば何が差別かが議論されるだろう。2024/04/01
kentaro
7
読んでいて胸が熱くなった。ヘイトはいけない、というだけでなく、どう抗していくか。こういう記者がまだいるのだ。⚫️差別をしない人はいない。誰でも、マイノリティでさえも、差別をしてしまうことがある。自覚的にも、無自覚的にも、「私は差別をしない」という人を、私は信じない。私は今後も、記者である限り反差別の記事を書き続けるし、人間である限り差別に反対し続ける。「私は差別をしない」では差別はなくならない。「私は差別に反対する。闘う」でなければならない。2021/04/17