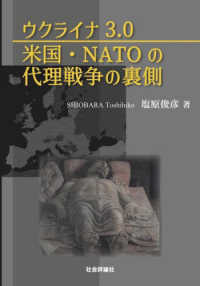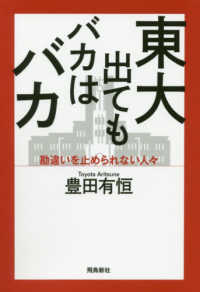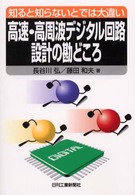出版社内容情報
江戸期に存在した知られざる異世界
鎖国時代、長崎に唐人屋敷という不思議な中国世界があった。徳川幕府の貿易の中心地は出島ではなく、この唐人屋敷だったのだ。高い塀に囲まれ、監視されていた唐人屋敷の実態を、資料をもとに読み解く。
内容説明
江戸時代の長崎に、唐人屋敷という中国ワールドがあった。鎖国政策を実施した徳川幕府の貿易の中心は、出島よりもこの唐人屋敷だったのだ。高い塀に囲まれた一画に、長崎奉行の厳しい監視のもと、多いときには二、三千人の中国人たちが暮らしていた。彼らは貿易を通じて、様々なモノや文化を日本にもたらした。特別な役人や遊女だけが入ることができたという唐人屋敷とは、どのような世界だったのか。残された史料や絵図をもとに、その実態を明らかにする。
目次
1 唐人屋敷の建設
2 唐人屋敷の生活
3 長崎にやってきた唐船
4 唐船貿易の変遷
5 中国文化が持ち込まれた長崎
6 唐人屋敷の終焉
著者等紹介
横山宏章[ヨコヤマヒロアキ]
1944年山口県生まれ。北九州市立大学大学院社会システム研究科教授。専門は中国政治・外交史。一橋大学法学部卒業後、同大学院法学研究科博士課程満期退学。法学博士。明治学院大学教授、県立長崎シーボルト大学教授を経て現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まりお
46
鎖国した日本の、唯一の貿易場所であった長崎。オランダとの貿易が有名であるが、中国、唐人との貿易が一番盛んであった。今は見る影もない唐人屋敷。この場所での貿易、生活、文化、規則、日本人との関わりなどを紹介。この貿易を取り締まる長崎の管理体制の中で、通訳を行う「唐通事」という職がある。これは屋敷が出来る前に日本に帰化した唐人達の子孫が世襲している。彼らは日本に受け入れてもらえた、それが驚きである。2017/07/02
feodor
7
鎖国、長崎というと出島のイメージが強いけれども、それよりもずっと大きな外国人居留地であった唐人屋敷についての著作。Q&A形式でいくのだけれども、ただに唐人屋敷のことだけでなく、結局は鎖国体制下の長崎貿易や、中国情勢のことについてもわかってなかなかにおもしろい。もともとの視点が「唐人屋敷ではどんな生活をしていたのか」というあたりからなので、そういったところも史料をうまく駆使して補われており、全体に鎖国体制下の長崎の様子がいきいきと描かれていておもしろかった。2011/09/25
150betty
2
(☆4)出島の華やかなりし頃の長崎では、遠くから来る都合上ガテン系の多いオランダ人よりも唐人のほうが教養がある人も多くて長崎の人たちはこぞって唐人たちと交流を望んだそうなのだけど。その辺りに興味が湧いて唐人を調べたくて読みました。長崎と唐人の関係はあんま本が出てなくてその中ではわりとまとまってる部類だと思う。色々な本で俎上に上がってるけど、遊ぶために当時中国から日本に結構旅行客が来てたというのは割に面白い。2014/04/22
釈聴音
2
著者が日本近世史の専門ではないため、全体的に史料の読み込みが浅く、項目の羅列に終わっている観が否めない。また一部史料の読み誤りかと思われる点が見られるのは残念である。しかし長崎の唐人屋敷という興味深い題材を紹介している点は価値ありといえる。2011/07/18
韓信
1
長崎に行くので読了。出島の陰に隠れがちだが、江戸時代の対外貿易の中心だった唐人屋敷の入門書。沿革、居住空間、食事、丸山遊女との逢瀬、抜け荷と犯罪、娯楽などの生活面と、生糸や銅が中心の唐船貿易の実情、長崎奉行・会所・唐通事など管理体制、唐寺や媽祖廟などの現代にも残された中国文化など、これから唐人屋敷に行く身には知りたい内容を一通り解説してくれて、先行研究の紹介も豊富で興味のある箇所を深掘りもできる好内容。カクレキリシタンが豚を飼養・屠畜して唐人屋敷や出島に供給していたなど、長崎の意外な一面も知れて面白い。2025/10/11
-
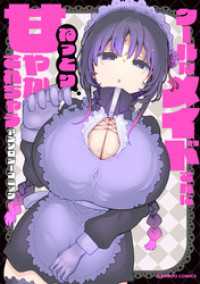
- 電子書籍
- クールなメイドさんにねっとり甘やかされ…
-
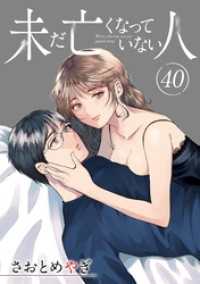
- 電子書籍
- 未だ亡くなっていない人【単話】(40)…