内容説明
日本の食料自給率は四〇%前後。その結果、私たちは、莫大な量の輸入食料に頼って日々の命をつないでいる。それがきわめて危険な状態であることを、どれほどの人が認識しているだろう。他の先進諸国のように、一〇〇%近い自給率を達成することは、この国では実現不可能な夢物語なのか?そうではない。真っ当な国家であれば、どんなに困難な道であろうとも、あくまで「一〇〇%」を目標とすべきなのだ。農と食の現場に立ち続ける著者が、食料自給率回復の志を説き、熱く提言する。
目次
第1章 食料自給率の低さが意味するものは?
第2章 農水省発表の自給率と実質自給率はなぜ違うのか
第3章 日本の農業政策は、なぜ自給率を低下させたのか
第4章 食料自給率低下による具体的な影響
第5章 食料自給率をめぐる世界の現状
第6章 食料自給率向上のために、どんな施策が必要か
第7章 「新しい地方の時代」が鍵となる
著者等紹介
島崎治道[シマザキハルミチ]
1939年静岡県生まれ。法政大学社会学部卒業。法政大学社会学部兼任講師(「農業・食料論」担当)、同大学院「食と農」研究所特任研究員。90年から01年まで、埼玉県「二一世紀むらづくり塾」アドバイザーをつとめる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
19
その時になってからでは遅いのだが。。。2009/12/28
とうゆ
16
食糧自給率が低い上に、農作物や畜産物の生育すら、自国で完結できていないという恐ろしい話。ただ、少しデータが少ないかな。例えば、小麦の自給率を上げなければならないと書いてあるけど、日本の国土に小麦に適した土地はどれくらいあるのだろうか。この問題が余り注目されないのは、今がグローバリズム全盛の時代だからではないだろうか。食料を輸入することが全く出来ない状況を、想像できない時代だ。ある種の、平和ぼけなのかもしれない。2015/06/10
桃水
4
2010/05/09:日本の食料自給について書かれた本ですが、視野が狭く誘導的で政府批判が強いです。高付加価値作物について水気耕栽培を勧めていていますが、水気耕栽培は初期投資が高いだけでなくランニングコストも高いです。殆どハウス物と差はないのに高く売れるはずもなく、机上の空論。2010/05/09
1.3manen
3
毎年のようにカロリーベースの自給率が約四割となっていて大きな変動がないデータもめずらしい。確か『農業経営者』の計算では66%だった。それでも多くは輸入に頼っている。自給率を上げるには地産地消や食べ残さないことが学生から提起されたようだ。他に耕作放棄地を減らしてTPPに参加しない路線もありはしないか。私はTPPだと過剰在庫はゴミになると思う。増税でスタグフレーンョンを懸念する。2012/08/20
夏至
2
唐突に、ではないけど、SDGsの勉強してたときかな、日本の食料自給率を高めることに対して、私たち一般市民ができることって国産を選んで買う、くらいなのかなって興味があって読んだ。ちょっと古い本か版ではあったけど、基本的に自給率のUPは国の政策であるところが大きく、また政治に求めることが増えてしまった…という感じ。私たちができるのは食べ残さない、なるべく生産地に近いところの物を買う、規格外など健康上問題ないものを許容する(広い意味でフードロスか)というところか。2022/07/16
-
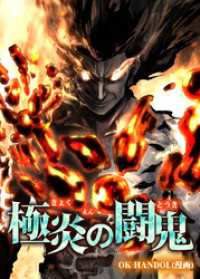
- 電子書籍
- 極炎の闘鬼【タテヨミ】第34話 リバース
-
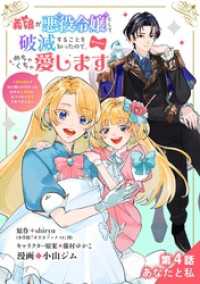
- 電子書籍
- 義娘が悪役令嬢として破滅することを知っ…
-
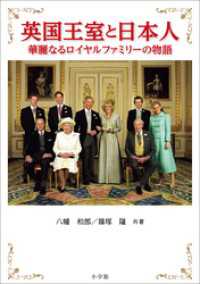
- 電子書籍
- 英国王室と日本人 ~華麗なるロイヤルフ…
-
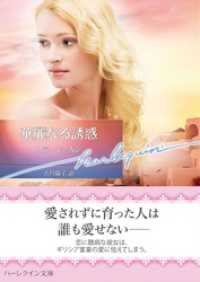
- 電子書籍
- 華麗なる誘惑【ハーレクイン文庫版】 ハ…





