内容説明
北斎をはじめとする江戸の浮世絵師たちにとって、版本の挿絵は重要な仕事であり、そこには、物語作者とのコラボレーション、対決を通じての創造のあくなき追求を見ることができる。北斎・馬琴の『新編水滸画伝』『椿説弓張月』から無名の作者、絵師の作品に至るまで、幽霊や妖怪、異界のものたちが跋扈し、生首が飛び、血がしたたる、残虐とグロテスクに満ちた「奇想」のエネルギーが横溢しており、斬新な技法、表現、意匠の実験が絶えずくりかえされている。本書は、この膨大な版本の世界を渉猟し、新発見の図版などから、現代のマンガ・劇画・アニメにまで流れる日本の線画の伝統の大きな水脈をたどり、その魅力と今日性を浮き彫りにする。
目次
はじめに 江戸後期挿絵の魅力
第1章 「異界」を描く
第2章 「生首」を描く
第3章 「幽霊」を描く
第4章 「妖怪」を描く
第5章 「自然現象」を描く
第6章 「爆発」と「光」を描く
第7章 デザインとユーモア
著者等紹介
辻惟雄[ツジノブオ]
1932年、名古屋市生まれ。東京大学・多摩美術大学名誉教授、MIHO MUSEUM館長。東京大学大学院博士課程中退、東京国立文化財研究所美術部技官、東北大学文学部教授、東京大学文学部教授、国立国際日本文化研究センター教授、千葉市美術館館長、多摩美術大学学長などを歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 部長から義兄、そして恋人!? 1 素敵…
-
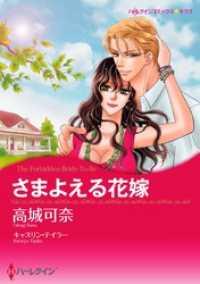
- 電子書籍
- さまよえる花嫁【分冊】 5巻 ハーレク…
-
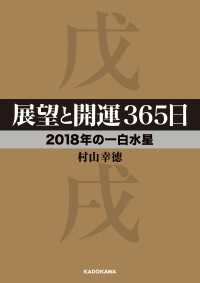
- 電子書籍
- 展望と開運365日 【2018年の一白…
-

- 電子書籍
- AYURI - 今野鮎莉写真集
-
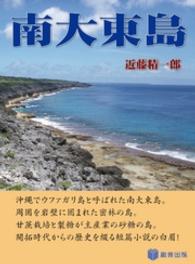
- 電子書籍
- 南大東島



