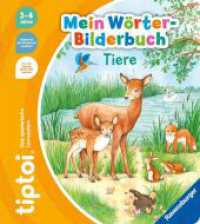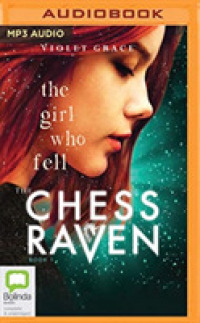内容説明
日本の食料自給率は、年々低下を続け、カロリーベースでは40パーセント、穀物自給率では二七パーセントになってしまった(1998年度)。それでも「飽食の時代」を謳歌できるのは、外国からの大量の食料輸入に頼っているからである。「瑞穂」の国といわれた日本は、天候不順や蝗害などでたびたび「飢饉」に襲われてきた歴史がある。絶対的な飢えに直面した時、人々はどんな行動をとるのだろうか。そして「飢饉」はどんな社会経済構造の下で起きるのだろうか。本書は飽食の時代に警鐘を鳴らす「飢えと食の日本史」である。
目次
序章 今、なぜ飢饉か
第1章 日本列島の飢饉史
第2章 飢饉のなかの民衆
第3章 凶作・飢饉のメカニズム
第4章 飢饉回避の社会システム
第5章 飢饉の歴史と現代
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
キクチカ いいわけなんぞ、ござんせん
20
飢饉は人災であると。政府の無策。いつの世も変わらん。2016/10/07
姉勤
19
幸い、飢えること無く生きてこれた。江戸期に起きた大飢饉と明治以後の凶作。日照りや冷害、虫害獣害、そして穀物の流通換金システム。これらによって人々は飢え、仕舞には隣人が共に相食むやるせない餓鬼世界へ。米は基準の換金作物で、地方から都市に流れ、地方は売った金で運営された。一旦そのバランスが崩れれば、飢餓となる。良いものを安く世界からと謳うグローバル経済。この飢饉を生み出したシステムと何が違うのか。太陽と火山の活動、海流のバランスが崩れただけでも、穀物の生産量は落ちるのだ。無いものを安く売るバカが居るのか。2014/11/02
Humbaba
8
人身売買.それは,人権というものが完全に無視された行いである.確かにそのようなことを行ってはいけないというのは,何時の時代でも成り立つだろう.しかし,飢饉によって食物がなく,人身売買によって家族も,そして売られた人間も命だけはつなげるとしたら,選択肢の一つとなることは免れ得ないであろう.2012/02/01
お萩
7
飢餓といえば、旱魃で作物が育たない→食べるものが無い→餓死、くらいの認識しかないほど生活からかけ離れた現象のように思っていたけれど、本書を読んで認識が変わった。決して天候だけが飢饉の原因ではないこと、決して過去のことではないという事が分かりやすくまとめてある。2016/02/16
ぐうたらパンダ
4
飢饉というのは気象のせいでなるとばかり思っていたが、江戸時代のイノシシ飢饉など政治的な影響が自然現象と同じか、もっと大きいことを知った。今も同じか…2012/07/29
-
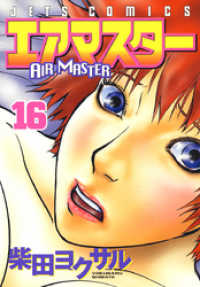
- 電子書籍
- エアマスター 16巻 ヤングアニマルコ…