感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
匠
107
やはり睡蓮を描いた作品の数々がとても好きだけれど、全体を蒼の濃淡で統一した『ジヴェルニー近郊のセーヌの流れ』がとても落ち着けて見飽きない。また、縦横約30センチのサイズは画集としてとても見やすく、ありがたい。代表作62点ほどとわかりやすい解説を年代順にではなく、画家独自のテーマ、モチーフに分けた構成になっているのが特徴。白内障で失明寸前の状態でもなお描き続けたモネの、光の効果を画面に定着させた神髄が解明されていて興味深い。そうそう、文字も大きめで読みやすかった。2014/02/13
つくよみ
73
図書館本:オスカル=クロード・モネ(1840-1926)彼の作品「印象・日の出(1873)」から「印象派」の名称が生まれた事でも有名な、印象派の旗手。その作品を62点収めた画集。『日本の太鼓橋(1899)』についての考察文と、エッセイ、評伝も収録。「積み藁」「ポプラ」「ルーアン大聖堂」そして「睡蓮」等の、同じモチーフを描いた連作が生まれたのは、彼が、移ろい行く瞬間瞬間の光を追い求め、画布に留めた結果だと言う。そんな画家の観た「光」そのものを、追体験させてくれるような作品群だった。2014/02/15
Mijas
42
大好きな「ジヴェルニーの庭」を見たくなった。つるばらのアーチは美しく、色とりどりの花々は悦びに満ち溢れ、さざ波のように光きらめく。図版でも充分魅了された。アルジャントュイユ時代を想わせる作品だが、「アルジャントゥイユの画家の家」(1873年)にはカミーユとジャンが描かれ、幸福そのものに見えるだけに胸が詰まった。そして白内障におかされた作品「つるばらの小路」(1922年)を見た。花が咲き乱れる庭の小路ではない。モネの歓喜と苦悩が収められた画集。ジヴェルニーの家の近郊図やセーヌ川沿いの制作地の地図も興味深い。2015/10/29
燃えつきた棒
24
吉川一義『プルースト美術館』からミシェル・ビュッシ『黒い睡蓮』を経由して、本書にたどり着いた。/ 【ブーダンによれば「風が断崖の端に至り、海に向かって飛び立つ時の大きなうなり」、また水の冷たさや空気の乾き具合までも、光のなかで感知され、色彩として画布に定着させられねばならない。自然を直接描くとはそういうことなのだった。】/ この様な風景描写を実現した文学がどこかにあるだろうか?/2025/05/27
ココアにんにく
0
モネ展開催まで待ちきれなかった。図書館で読む。以前モネ展に行った時鳥肌がよみがえった。美術のことはまったく知らないけど、本物を見てみたいという好奇心から美術展には機会があるごとに通っている。31×31の大きな本なので実物の印象がよみがえる。後半の文章でうんちくも仕入れることができた。ヒケラカシたい!モネとルノワールが画架を並べる姿を勝手に想像して感動しています。2016/02/26
-

- 和書
- さかなの出現 シリーズ海


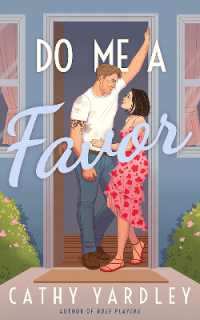
![中国語繁体字版 クスノキの番人 [バラエティ] 春日文庫 86](../images/goods/ar2/web/imgdata2/44085/4408537616.jpg)



