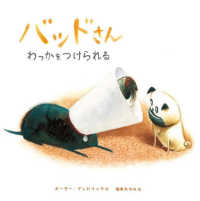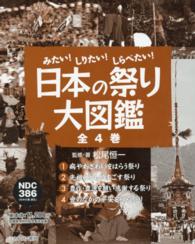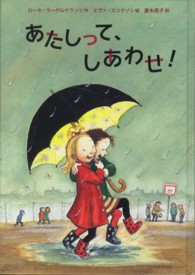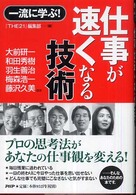内容説明
きもの嫌いだった人間が、京都に来て、いろんな人たちとの出会いから、きものに心を開いていく様子を経糸に、着付け、染替え、手入れ、小物選びなど、実用的なことを緯糸にしながら、十九の文様に織り上げたのが、このエッセイ集です。
目次
覚める
結ぶ
育む
滴る
閃く
考える
継ぐ
著者等紹介
麻生圭子[アソウケイコ]
1957年大分県生まれの東京育ち。作詞家を経て、現在はエッセイスト。96年に再婚し、京都に移る。99年には築70数年の小さな町家を借り、建築家の夫とともに、昔ながらの工法で修復。さらに05年には築80年の町家に引っ越し、京都の伝統とのさらなる出会いを深める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
百花
2
人気作詞家からエッセイストへ。そして東京から京都へ住まいを移され、若い頃には興味のかけらすら無かった着物への熱を軽やかに、そして謙虚に語る著者。女性に生まれたら一度は着物に手を通したくなるのではないか。そう思うのは私だけか。著者は四十を前にして目覚めたそうだが、その好みというのがなんとも渋い。スタイルがよくお綺麗だから、渋い着物がとても良く似合う。心に留めおきたい言葉が幾つもあったが、いつものこと、本を閉じたら見事に忘れてしまった。2018/12/28
みっくん
2
図書館で借りた本なので帯は無。うーん、これは帯ごとカバーリングして欲しかった。初心者時代から、凝り始めた頃まで入っているので面白いです。紹介されている帯の織元さん。私も大好きです。長襦袢の袖裏が色違いは市販でもあります。持ってます。お洒落だけれど、長着を選ぶんですよね。 名言:「きものは春は花、夏は風鈴、秋は月、冬は日向に自分がなること」by渡文の社長さん、夏は涼しげに見えるのが一番の粋 2015/03/01