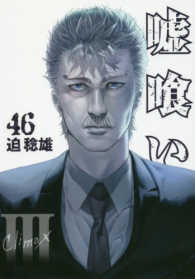内容説明
旧石器時代から縄文時代をへて稲作文化の伝来に至る日本列島における歴史誕生の謎をすべてわかりやすく解説。隣接諸科学の最新のデータを駆使し、国際的視野から日本文化形成のプロセスを克明に追求した話題の書。
目次
はじめに 「日本史誕生」を考える―現在と過去、アジアと日本
第1章 日本列島の旧石器時代
第2章 縄文文化の誕生
第3章 山の幸・海の幸を求めて
第4章 縄文のムラと社会、くらしと祭り
第5章 アジアの中の縄文文化
第6章 縄文人から現代人へ
第7章 稲作文化の伝来と展開
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
やいっち
74
「土偶を読む」続いて「土偶を読むを読む」も読んで、改めて縄文時代から弥生時代の流れを30年ぶりに本書で学び直し。「日本人はいつ頃、列島に住みついたのか? 100万年以前の古代から弥生時代の初期にいたる謎の古代日本を、民族学の立場から探る」とあるが、著者は専門を越えた幅広い知見を踏まえて説いてくれる。今日からしたら古くなった説明もあるが、それでも読むべき本に変わりない。2024/01/15
やいっち
51
いま読んでる「土偶を読むを読む」にて本書(の著者)に言及されてる。まさか30年後に再会するとは。民族学者(としての佐々木)と考古学者との複雑骨折してる関係。
bluemint
6
日本の成り立ちがよく理解できた。一万年続いた縄文時代の文化は弥生時代に稲作を伴った外来文化が入ってきても駆逐されず、日常的な生活文化は残り、今に至るまで日本人の文化の基盤を形成している。ヒトとしての日本人は古モンゴロイドが占めていた旧石器時代人と、寒冷気候に適応した後参入の新モンゴロイドとのハイブリッドである。日本語は遥か昔の東南アジアの共通祖語をベースに、縄文中期、弥生初期に入ってきた言語が混ざり古代日本語が出来たと考えられる。しかし、数千年も経ているので元の言語を辿ることができない。2021/05/17
おーちゃん
2
アジア圏の遺伝の見分け方で指の渦巻きでわかるのが面白かった。旧石器時代が日本には無いと思われていた事が、相沢忠洋によってわかるのだけど、そこのところの雰囲気を上手に伝えてくれていたのがとても良かった。民族学や、焼畑を通じてのアジアの植生などの視点が入った日本の理解ができる本。2022/05/22
めっかち
2
日本の縄文時代が他のそれに比しても生活レベルが高いものであった点が興味深い。東西で様々な差異がみられるというのも。
-

- 電子書籍
- 黒パン俘虜記(新装版)