内容説明
100年余に及ぶ大衆文学の通史。円朝の講談・人情噺の速記本化、立川文庫の活況、「大菩薩峠」の執筆開始などの前史をふまえ、大衆文学の成立から今日の隆盛までを、あまたの作家の人と作品にふれながら描きあげた著者100冊目の記念碑的労作。戦前篇、戦後篇に分冊。
目次
戦前篇(速記と三遊亭円朝;板垣退助の洋行土産;村上浪六の撥鬢小説;鞍馬天狗の誕生;大仏次郎の特異性;「キング」の創刊;情話から小説へ―村松梢風;直木三十五の立場;吉川英治の年輪;直木賞の制定;邦枝完二とお伝;山手樹一郎と明朗時代物;戦時下の強圧;富田常雄と柔道小説;山岡荘八の曲折 ほか)
戦後篇(石坂洋次郎における津軽;今日出海の比島戦記;獅子文六の諷刺;五味康祐と剣豪小説;戸川幸夫と動物小説;水上勉の文学遍路;司馬遼太郎とその史観;梶山季之と社会;有吉佐和子と三代記;野坂昭如の意地;筒井康隆のパロディ;井上ひさしの諷刺;星新一とショート・ショート;半村良と伝奇SF ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
rbyawa
0
h089、大衆文学という概念と言葉自体は大正末から昭和初期くらいまでに生じ、そう呼ばれることになったきっかけは白井喬二の雑誌、中里介山の指摘ではあるいは皮肉なのではないかと言われているようで。この本で語られていたのは主に「新講談」と呼ばれていた分野から出てきた人たちが主。数が多く必要となる分、どうしてもマンネリに陥るという欠陥に関しては納得。しかし純文学との比較に関してはその議論自体がどうにも泥縄かなぁ…。あちらの歴史もわりとまあ、しょうもない手抜きされた小説でブレイクして有名になるのがパターンだしねぇ。2017/12/30
-
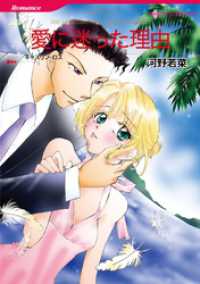
- 電子書籍
- 愛に迷った理由【分冊】 7巻 ハーレク…
-

- 電子書籍
- METAL HAMMER JAPAN …
-

- 電子書籍
- エクセル仕事の自動化が誰でもできる本
-
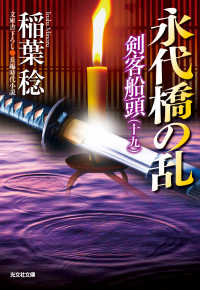
- 電子書籍
- 永代橋の乱~剣客船頭(十九)~ 光文社…
-
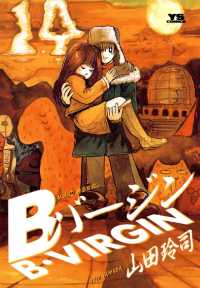
- 電子書籍
- Bバージン(14) ヤングサンデーコミ…




