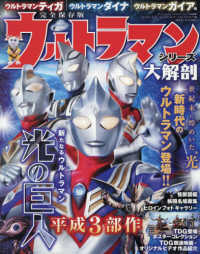- ホーム
- > 和書
- > 新書・選書
- > 教養
- > 講談社ブルーバックス
出版社内容情報
約2億5000万年前、史上最大とされる大量絶滅が起きた。海棲生物では生物種の96%が絶滅したという研究もある。シベリア・トラップの火山活動が原因とされているが、大量絶滅のメカニズムについてはまだわからないことが多い。しかも、海と陸、無脊椎動物と脊椎動物、植物では、絶滅の起きたタイミングや規模に差があるようなのだ。従来の研究では、海棲生物、それも化石が多く残っている無脊椎動物の研究が中心となっていた。本書では、海棲無脊椎動物の研究からだけでは見えてこない、生物界全体にとっての、ペルム紀末の大量絶滅を描き出していく。そもそもペルム紀とはどんな時代だったのか? ペルム紀末には何が起きたのか? 三畳紀には生物とそれらを取り巻く環境はどのように回復していったのか? 史上最大の大量絶滅という大テーマを包括的に扱った野心的な一冊。
目次
序章 そのとき何があったのか?
第一部 前夜
第一章 境界前の席巻者 単弓類
第二章 黎明期の登場者 陸棲爬虫類
第三章 古き良き・・・・・・ 両生類
第四章 消えゆく海の主役たち サカナ
第五章 海底の窓から見ると 軟体動物
第二部 世界をまたいで
第一章 植物が紡ぐ
第二章 昆虫が紡ぐ
第三部 新たな時代
第一章 時代を譲る 単弓類
第二章 時代を握る 陸棲爬虫類
第三章 勃興する 海棲爬虫類・両生類
第四章 新世界のメンバー サカナたち
第五章 世界の目撃者たち 軟体動物・棘皮動物
終章 そのとき何があったのか?
【目次】
内容説明
生物の分類群ごとに見ていくと「大量絶滅」観が変わる。ペルム紀末に海棲生物種の96%が絶滅したといわれている。じつは陸上生物の数字はもっと低く見積もられており、植物では、大量絶滅の影響は大きくはなかったという研究もある。「ペルム紀末に大量絶滅が起きた」という一言ですむほど、単純なことではなかったらしい。生物の分類群ごとに見ていくと、大量絶滅の影響は規模も時期も、それぞれ少しずつ異なっていたようだ。では、実際には何が起きたのか?分類群ごとにその影響を調べ、またその回復後の世界まで描いて、大量絶滅をマクロとミクロの両方の視点からとらえる。
目次
そのとき何があったのか?
第1部 前夜(境界前の席巻者―単弓類;黎明期の登場者―陸棲爬虫類;古き良き…―両生類 ほか)
第2部 世界をまたいで(植物が紡ぐ;昆虫が紡ぐ)
第3部 新たな時代(時代を譲る―単弓類;時代を握る―陸棲爬虫類;勃興する―海棲爬虫類・両生類 ほか)
そのとき何があったのか?
著者等紹介
土屋健[ツチヤケン]
オフィスジオパレオント代表。サイエンスライター。日本古生物学会会員、日本地質学会会員、日本文藝家協会会員。金沢大学大学院自然科学研究科修了。修士(専門は地質学、古生物学)。科学雑誌『Newton』の編集記者、部長代理を経て、2012年に独立し、現職。2019年、サイエンスライターとして初めて、日本古生物学会貢献賞を受賞
大山望[オオヤマノゾム]
山口大学理学部地球圏システム科学科卒業、九州大学大学院にて博士課程修了。九州大学総合研究博物館技術補佐員、同専門研究員、日本学術振興会海外特別研究員(パリ国立自然史博物館、パリ古生物研究センター)を経て福井県立大学恐竜学部助教、福井県立恐竜博物館研究員。専門は古生物学、古昆虫学、地積学、化石化過程
木村由莉[キムラユリ]
早稲田大学教育学部卒業。米国・サザンメソジスト大学地球科学科にて修士および博士課程修了。スミソニアン国立自然史博物館等でのポスドクを経て、2015年、国立科学博物館着任。2021年より国立科学博物館生命史研究部進化古生物研究グループ博士研究員研究主幹。専門は、哺乳類古生物学
重田康成[シゲタヤスナリ]
1992年、東京大学大学院理学系研究科地質学専攻博士課程修了。博士(理学)。現職は国立科学博物館生命史研究部環境変動史研究グループ長、筑波大学連携大学院教授(兼任)。専門は古生物学、地質学
對比地孝亘[ツイヒジタカノブ]
フィールド自然史博物館ポストドクトラル研究員、国立科学博物館特別研究生(地学研究部)、国立科学博物館短時間非常勤研究員(地学研究部)、日本大学文理学部地球システム科学科非常勤講師、東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻講師を経て、東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻准教授(委)、国立科学博物館生命史研究部進化古生物研究グループ研究主幹。専門は、古脊椎動物学、脊椎動物比較解剖学
中島保寿[ナカジマヤスヒサ]
2013年、東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻博士課程修了。博士(理学)。日本学術新興会海外特別研究員(ボン大学シュタインマン研究所)、日本学術振興会特別研究員(東京大学大気海洋研究所)を経て、2018年より東京都市大学理工学部(当時は知識工学部)自然科学科准教授。専門は古生物、進化生物学
宮田真也[ミヤタシンヤ]
2014年、早稲田大学創造理工学研究科地球・環境資源理工学専攻博士諜程修了。博士(理学)。早稲田大学理工学術院招聘研究員、秀明大学学校教師学部理科専修助教を経て、現職は、学校法人城西大学水田記念博物館大石化石ギャラリー学芸員、城西大学理学部助教。専門は魚類化石の分類学、現生魚類の骨学
矢部淳[ヤベアツシ]
筑波大学大学院地球科学研究科中退。2011年、千葉大学大学院理学研究科論文博士(理学)。福井県立博物館、福井県立恐竜博物館研究員を経て、国立科学博物館生命史研究部進化古生物研究グループ長。専門は古植物学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
- 評価
COSMOS本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
旅するランナー
ホークス
とも
春風
Tomonori Yonezawa
-

- 電子書籍
- 復讐タワーマンション 妹を殺したのは誰…