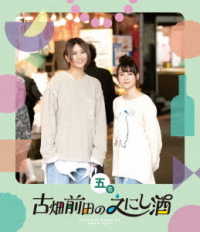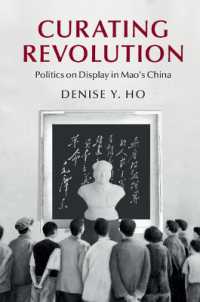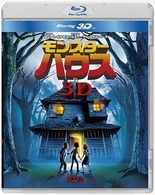出版社内容情報
認知症ケアの新しい技法として注目を集める「ユマニチュード」。
わたしたちが介護をするときに困ってしまう
認知症の周辺症状(妄想・暴言・不安・幻覚・不眠・徘徊・・・etc)は
認知症の方の不安な気持ちがきっかけになって発症します。
本書はわたしたちが見ている「今」ではなく
認知症の方が見ている「今」に飛び込み、
ご本人の不安な気持ちを取り除く技術を「介護シーン別」に徹底解説。
「お風呂に入ってくれない」
「食事を食べてくれない」
【目次】
【Chapter1】 認知症の方が笑顔になる「ユマニチュード」4つの柱
・こんな困ったは「不安のサイン」
・ユマニチュード「4つの柱」
【Chapter2】記憶の仕組みとユマニチュードの役立て方
・私たちの生活は「記憶」で支えられている
・記憶は「五感」によって情報を脳に定着させている
・短期記憶(記憶は30秒しかもたない)
・脳の機能低下で起こる認知症の「中核症状」
・不安感によって引き起こされる「周辺症状」
【Chapter3】人生
内容説明
ユマニチュードとは、「あなたのことを大切に思っています」と相手が理解できるように伝える認知症のケア技法です。1979年フランス発祥で、世界13ヵ国で普及しています。日本では2012年頃から普及し始め、介護や看護の現場に限らず、自宅での介護においても広く用いられています。ユマニチュードの技術を身につけることで、介護を受ける方の「周辺症状(行動心理症状)」は自然となくなり、再びご本人と意思疎通がとれるようになります。
目次
1 認知症の方が笑顔になる「ユマニチュード」4つの柱(こんな困ったは「不安のサイン」;ユマニチュード「4つの柱」)
2 記憶の仕組みとユマニチュードの役立て方(私たちの生活は「記憶」で支えられている;記憶は「五感」によって情報を脳に定着させている ほか)
3 人生の「生活史」をケアに活かす(思い出はケアの核になる;手に取れる「好きなもの」を身近に置く ほか)
4 認知症の方が笑顔になる言葉と話し方(ケアの現場での「話し方」;いきなり要件を切り出さない ほか)
5 ケアの手順「ユマニチュード式」5つのステップ(ユマニチュードのケア「5つのステップ」;意思の疎通が取れない ほか)
ユマニチュードの5原則
著者等紹介
本田美和子[ホンダミワコ]
東京医療センター医師。1993年筑波大医学専門学群卒。内科医。亀田総合病院、米国コーネル大学老年医学科などを経て、2011年より日本でのユマニチュードの導入、実践、教育、研究に携わり、その普及・浸透活動を牽引する。国立病院機構東京医療センター総合内科医長/医療経営情報・高齢者ケア研究室室長
ジネスト,イヴ[ジネスト,イヴ]
「ユマニチュード」の考案者。ジネスト‐マレスコッティ研究所長。フランスのトゥールーズ大学卒業(体育学)。1979年にフランス国民教育・高等教育・研究省から病院職員教育担当者として派遣され、病院職員の腰痛対策に取り組んだことを契機に、看護・介護の分野に関わることとなった(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Go Extreme