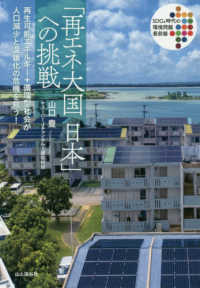出版社内容情報
暗算は得意なのに、なぜ日本人に理数嫌いが多いのか。その原因には、歴史的・構造的な要因があるのではないか?
物理学の泰斗がそんな素朴な疑問から、古来、人間の文化・文明に欠かせない「数の知識」と日本人社会とのかかわりを、たどってみるとーー。
12進法を使って土木建築を行ったといわれる縄文時代、ピタゴラスの定理で平城京を作り、飛鳥時代に日本初の元嘉暦を生む。奈良時代には正確な計測が不可欠な班田収授の法を採用するも、平安時代には「金勘定はいやしい仕事」と一気に理数離れが起こるーー。江戸時代の寺子屋と算術教育、日本初のサイエンス・和算の誕生、明治時代の算術から算数への大変換、そして戦後の数教育まで、5000年超の通史を豊富なエピソードで活写。理数科は単なる技術を支える手段ではない。数理に対する関心と尊敬心が高まる、ユニークな数学読本!/解説:上野健爾(京都大学名誉教授 四日市大学関孝和数学研究所長)
筆者の言葉)
「歴史家は数学に興味を持たない人が多く、科学史家はそれぞれの専門を守っている。理系に身を置いてはいるが、数学や歴史学に素人の筆者が本誌を書くに至ったのは、こんな事情であまり知られていない数の日本史に、現代人に強く訴えるものがあると感じたからである。
(中略) 社会の専門化によって閉塞感に悩んでいる現代知識人にとって、日本文化の意外な再発見と解放感をもたらすだろう」
目次
第1章 古代の数詞
第2章 大陸数文化の興隆
第3章 漢数字、数文化の到来
第4章 平安、中世の数世界
第5章 数文化興隆の江戸時代
第6章 和算――世界に並んだ科学
第7章 洋算、その受容と現代社会
第8章 現代の数世界
解説:上野健爾(京都大学名誉教授 四日市大学関孝和数学研究所長)
【目次】
目次抜粋
第1章 古代の数詞
暁闇の旧石器時代/縄文時代は十二進法?/謎を秘める縄文尺/1万年の縄文時代/日本祖語と流入言語/古代日本数詞の起源/古代数詞の二重構造と表現/記数法はあったのか?
第2章 大陸数文化の興隆
漢民族の台頭/甲骨文――東洋初の数字/上数、中数、下数/算木/九章算術の出現/古代数学書はいま/唐の算学制度/唐で止まった巨大数・インド数字
第3章 漢数字、数文化の到来
西暦紀元後の東アジア/多かった空白時代の交流/現代数詞の三重構造/小数表現の弱さ/律令国家と数/養老令に見る算学/算に秀でた吉備真備/奈良時代の税務調書/暦法に現れる数/大事業だった写経/平城京はピタゴラスの定理で/班田収授を支えた算師/遺産相続は分数で/万葉集 遊び心の数世界/仮名文字の登場
第4章 平安、中世の数世界
「理数科離れ」の平安時代/衰退する算学、暦法/神楽歌に見る数字/宇津保物語/五雀六燕の術/おそろしきは算の道/口遊の九九/二中歴に見る算遊び/御伽草子に見る数/五山文学における数遊び/わが曾祖父は九九二翁/独立する算師/鎌倉時代の四捨五入/室町から戦国ヘ/室町時代の貨幣経済/そろばん登場/
第5章 数文化興隆の江戸時代
凡下の者/「算用記」をめぐって/割算の天下一/消化された「算法統宗」/吉田光由と「塵劫記」/塵劫記の変遷/塵劫記の構成/確定した数表現/奇妙な金銀の比重/生活密着の明和本/明快な絵解きそろばん/暗算の東西/問題、答、術、法/屋根の勾配問題/ゼロの表記法/複雑な貨幣交換/江戸は高金利時代/米経済は升目から/男女の比は2対3?/入子算、鼠算/塵劫記に見る巨大数/暮らしに密着した知的クイズ
第6章 和算――世界に並んだ科学
塵劫記を超えるもの/和算の端緒/キリシタンの影/東洋初の代数、天元術/世界初の二次元並列コンピュータ/尽と不尽/円周率の変遷/その頃の西欧数学/関孝和という人物/縦書き代数式の創出/点竄術とは/微積分はあったのか/深奥の和算/奇才、久留島義太/有馬侯秘伝を暴露/和算の感性・美学/庶民の和算/西洋数学の到来
第7章 洋算、その受容と現代社会
開国の圧力/長崎海軍伝習所/沼津兵学校/蕃書調所/維新10年、新教育体制/学制から高等教育へ/大村益次郎・柳河春三・菊池大麓/菊池大麓と和算/明治5年、8年の教科書/計算尺の盛衰/初等数教育の変遷/国定教科書の誕生/到達点、緑表紙/算術から算数へ
第8章 現代の数世界
社会における数変化と終戦/国定から検定へ/数学教育現代化問題/円周率は3でよい?/「学習禁止要領」/四捨五入の教え方/大学にまで及んだ学力低下/期待される数教育/数世界の進化と退化/ウエアラブルな数世界/これから必要な数知識/差と比の社会、桁違いの社会/十倍図で見る物の値段/毒物――致死量を見る/地震――マグニチュードの対数則/放射線――もっとわかりやすく/対数史観
内容説明
ピタゴラスの定理で作られた平城京。飛鳥時代に元嘉暦を導入し、奈良時代には正確な計測が必須の班田収授の法を採るも、平安時代には急激に理数科離れが進む…。五千余年、日本人は数や数学とどう付き合ってきたのか。正倉院保管の古文書や江戸の大ベストセラー「塵劫記」など豊富な史料から、歴史書では見えない日本を綴る!
目次
第一章 古代の数詞
第二章 大陸数文化の興隆
第三章 漢数字、数文化の到来
第四章 平安、中世の数世界
第五章 数文化興隆の江戸時代
第六章 和算―世界に並んだ科学
第七章 洋算―その受容と現代社会
第八章 現代の数世界
著者等紹介
伊達宗行[ダテムネユキ]
1929年、宮城県生まれ。東北大学理学部卒業。同大学院理学研究科物理専攻中退。物性物理学専攻。大阪大学名誉教授。日本物理学会会長、日本原子力研究所先端基礎研究センター長などを歴任。2023年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やいっち
へくとぱすかる
てつ
中村禎史
-

- 電子書籍
- 死ぬほど強くなれ【タテヨミ】 第051…