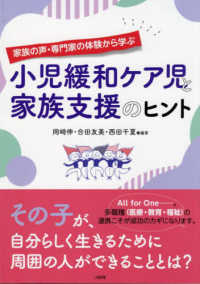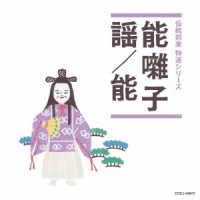出版社内容情報
「状況芳しくなく、腹は決まっています」
「これが最後の通信になるかもしれません」
「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」
最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……
何が写され、何が写されなかったのか?
兵士からは見えなかった〈もうひとつの戦場〉
「太平洋戦争勃発の際、ハワイでの奇襲攻撃は知っていても、その数時間前に日本軍の銀輪部隊(自転車部隊)がマレー半島を南下し、戦争勃発の引き金となった事実は、少なくとも日本では風化された記憶になっている。
一方で、戦争の被害を被ったマレーシアやシンガポールでは、こうした戦争の記憶は、学校や博物館だけでなく、家庭内でも継承され続けている。戦争に関する記憶のギャップは著しい。
世界で戦争や紛争が続く中、私たちにとって「戦後」とは何なのだろうか。
果たして、戦争の記憶を継承することはできるのか。
特派員たちは現場で何を見たのか。
ひとりひとりの仕事と人生を追うことで、知られざる「戦争の実態」が見えてくる」――「プロローグ」より
【目次】
第一章 戦争は報道を変えたか
第二章 特派員の叫びは新聞社首脳の耳に届いたか
第三章 戦時下中国で記者が取材したこととは?
第四章 帝国日本の周縁で何が起きていたか
第五章 南方で軍と新聞社は何をしていたのか
第六章 「不許可」写真は何を写していたか/写していなかったか
【目次】
第一章 戦争は報道を変えたか
第二章 特派員の叫びは新聞社首脳の耳に届いたか
第三章 戦時下中国で記者が取材したこととは?
第四章 帝国日本の周縁で何が起きていたか
第五章 南方で軍と新聞社は何をしていたのか
第六章 「不許可」写真は何を写していたか/写していなかったか
内容説明
最前線、連絡員の死、検閲…何が写され、何が写されなかったのか?兵士からは見えなかった〈もうひとつの戦場〉。戦争とは、戦後とは?彼らは戦火をどう生き抜いたのか?日中戦争から太平洋戦争、その後まで秘蔵写真が明かす〈本当に知りたかったこと〉
目次
プロローグ
第一章 戦争は報道を変えたか
第二章 特派員の叫びは新聞社首脳の耳に届いたか
第三章 戦時下中国で記者が取材したこととは?
第四章 帝国日本の周縁で何が起きていたか
第五章 南方で軍と新聞社は何をしていたのか
第六章 「不許可」写真は何を写していたか/写していなかったか
エピローグ 戦中写真は現代に何を問いかけるのか
著者等紹介
貴志俊彦[キシトシヒコ]
1959年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、ノートルダム清心女子大学国際文化学部教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
さとうしん
みさと
あられ
町営バス
-
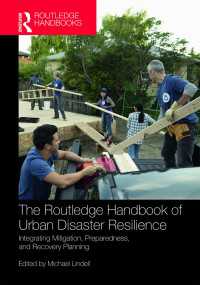
- 洋書電子書籍
- ラウトレッジ版 都市災害レジリエンス計…
-
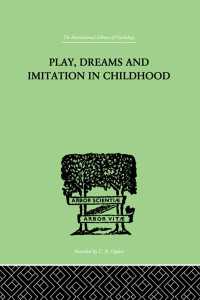
- 洋書電子書籍
- Play, Dreams And Im…