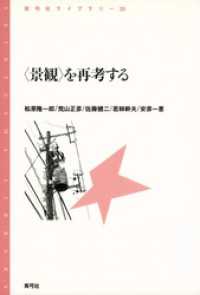出版社内容情報
子供はこっそり「悪書」に耽り、エリート学生は『善の研究』を通して「国体の本義」に自ら殉じていった――。
戦時下、人々は何を読み、何を考え、何になっていったのか。ベストセラーでも発行部数でもない、「読書調査」から掘り起こす、子供・勤労青年・女性・エリート学生たちの読書と生のリアル。統制と抵抗のはざまには、多様で複雑な読書と生の実践があった!
[目次]
はじめに 思想統制という幻像
序 章 読書は国家のために?――読書調査と思想統制
第一章 子供は見てはいけない――「悪書」の誕生
第二章 勤労青年は何を求めたか――娯楽と修養のはざまで
第三章 銃後女性の読書とその動員――忘れられた小説と忘れてはならない小説
第四章 ファシズムとエリート学生との回路――愛と認識との行方
終 章 読書を掘り起こす――「見えない」読者を追って
おわりに 読書傾向調査の系譜
注
あとがき
【目次】
はじめに 思想統制という幻像
序 章 読書は国家のために?――読書調査と思想統制
第一章 子供は見てはいけない――「悪書」の誕生
第二章 勤労青年は何を求めたか――娯楽と修養のはざまで
第三章 銃後女性の読書とその動員――忘れられた小説と忘れてはならない小説
第四章 ファシズムとエリート学生との回路――愛と認識との行方
終 章 読書を掘り起こす――「見えない」読者を追って
おわりに 読書傾向調査の系譜
注
あとがき
内容説明
戦時下、人々は何を読み、何を考え、何になつていったのか。子供・勤労青年・女性・エリート学生…都市・農村…ベストセラーや発行部数からは明らかにならない、各階層・各地域の読書と生のリアルを、戦前・戦中になされた「読書調査」から掘り起こす。統制され、抗い、適応し、殉じていく、多様で複雑な戦下の読書の実践に目を凝らす、未踏の研究の精華。
目次
はじめに 思想統制という幻像
序章 読書は国家のために?―読書調査と思想統制
第一章 子供は見てはいけない―「悪書」の誕生
第二章 勤労青年は何を求めたか―娯楽と修養のはざまで
第三章 銃後女性の読書とその動員―忘れられた小説と忘れてはならない小説
第四章 ファシズムとエリート学生との回路―愛と認識との行方
終章 読書を掘り起こす―「見えない」読者を追って
おわりに 読書傾向調査の系譜
著者等紹介
和田敦彦[ワダアツヒコ]
1965年、高知県生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。博士(文学)。現在、早稲田大学教育・総合科学学術院教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
軍縮地球市民shinshin
そうたそ
iwasabi47
えびちゅん