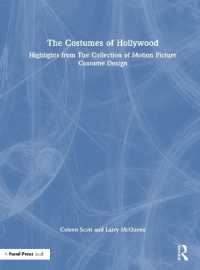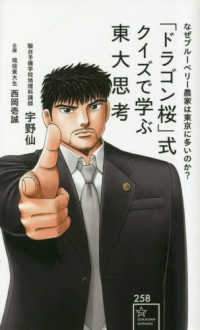出版社内容情報
蜘蛛が網を作ると、「恋しい人がやってくる」と喜んだ平安貴族。弥生人はその姿を銅鐸に刻み、ペルーの古代人はナスカ台地の砂漠に描き、ギリシアから北米まで、蜘蛛は世界の神話に数多く登場する。
時に畏れ、嫌い、崇め、慈しむなど、評価は極端。なのに、なぜか惹かれずにはいられない……。
人と蜘蛛のそんな不思議な関係を、日本中世史研究家が貴重な図版・史料とともに丁寧に考察。
蜘蛛愛好家の筆者だからこそ見えてくる、新しい歴史研究!
「内容紹介」
清少納言は、現代人よりもはるかに虫好きだったのだ。いささか厄介な虫たち、蠅、蟻、蚊、蚤について、「憎し」と言いながら、面白がってその生態を見つめ、魅力的に描写した女性がいた。清少納言である。(中略)
蜘蛛についても、網にかかった白露を、「をかし」「あはれ」の両方を使って絶賛している。
こうした眼差しは、どこへ行ってしまったのだろうか。いま、人間が虫に対して抱いてきた感情、心性、文化を見直し、つき合い方を考えることは、急務であると思われる。
―――本書 はじめに より
目次
はじめに
第一章 遺跡の蜘蛛・神話の蜘蛛
1 蜘蛛とはどんな生きものか
2 蜘蛛の考古学
3 世界の神話の蜘蛛たち
第二章 敵の名は土蜘蛛
1 征服神話の中の土蜘蛛たち
2 土蜘蛛は蔑称か
第三章 蜘蛛に寄せる恋の歌
1 蜘蛛に寄せる恋の歌
2 東アジアのめでたいしるし
3 蜘蛛と七夕
第四章 空を飛ぶ蜘蛛
1 雪迎え――空飛ぶ蜘蛛の発見
2 漢詩と和歌に詠まれた遊糸
3 「かげろふ」をめぐる混乱
4 『かげろふ日記』の「かげろふ」とは何か
5 十二単を飾る糸ゆふ
第五章 蜘蛛は神仏のお使い
1 蜘蛛は知る者、賢い者
2 あの人も蜘蛛に助けられた
第六章 妖怪土蜘蛛登場
1 蜘蛛嫌いの萌芽
2 寺蜘蛛の登場
3 よみがえった土蜘蛛
第七章 民俗と遠い記憶
1 相撲を取る蜘蛛
2 蜘蛛の昔話
3 夜の蜘蛛・朝の蜘蛛
おわりに ――蜘蛛はともに生きる仲間
参考文献
内容説明
蜘蛛が網を作ると、「恋しい人がやってくる」と喜んだ平安貴族。弥生人はその姿を銅鐸に刻み、ペルーの古代人はナスカ台地の砂漠に描き、ギリシアから北米まで、蜘蛛は世界の神話に数多く登場する。時に恐れ、嫌い、崇め、慈しむなど、評価は極端。なのに、なぜか惹かれずにはいられない…。人と蜘蛛の、そんな不思議な関係を、日本中世史研究家が貴重な図版・史料とともに丁寧に考察。蜘蛛愛好家の筆者だからこそ見えてくる、新しい歴史研究!
目次
第一章 遺跡の蜘蛛・神話の蜘蛛
第二章 敵の名は土蜘蛛
第三章 蜘蛛に寄せる恋の歌
第四章 空を飛ぶ蜘蛛
第五章 蜘蛛は神仏のお使い
第六章 妖怪土蜘蛛登場
第七章 民俗と遠い記憶
著者等紹介
野村育世[ノムライクヨ]
1960年、東京都生まれ。日本中世史研究者。東京蜘蛛談話会会員。早稲田大学大学院文学研究科(日本史専攻)博士後期課程満期退学。博士(文学)。高知県立高知女子大学助教授、早稲田大学非常勤講師を経て、現在、女子美術大学付属高等学校・中学校教諭(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
∃.狂茶党
バッシー
狐狸窟彦兵衛
Y.T
young
-
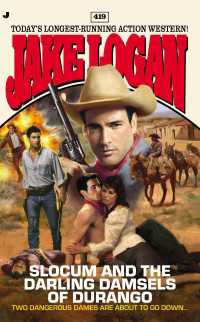
- 洋書電子書籍
- Slocum 419 : Slocum…