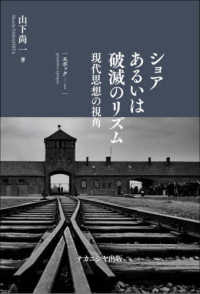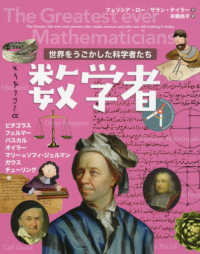出版社内容情報
チャットGPTに代表される生成AIは、機能を限定されることなく、幅広い学習ができる汎用性を持っている、そのため、将来、AIが何を学ぶかを人間が制御できなくなってしまう危険は否定できない。しかし、だからといって、AIが自我や意識を獲得し、自発的に行動して、人類を排除したり、抹殺したりするようになるだろうか。この命題については、著者はそのような恐れはないと主張する。少なくとも、現在の生成AIの延長線上には、人類に匹敵する知能と自我を持つ人工知能が誕生することはない、というのだ。
その理由は、知能という言葉で一括りされているが、人工知能と私たち人類の持つ知能とは似て非なるものであるからだ。
実は、私たちは「そもそも知能とはなにか」ということですら満足に答えることができずにいる。そこで、本書では、曖昧模糊とした「知能」を再定義し、人工知能と私たち人類が持つ「脳」という臓器が生み出す「ヒトの知能」との共通点と相違点を整理したうえで、自律的なAIが自己フィードバックによる改良を繰り返すことによって、人間を上回る知能が誕生するという「シンギュラリティ」(技術的特異点)に達するという仮説の妥当性を論じていく。
生成AIをめぐる混沌とした状況を物理学者が鮮やかに読み解く
本書の内容
はじめに
第0章 生成AI狂騒曲
第1章 過去の知能研究
第2章 深層学習から生成AIへ
第3章 脳の機能としての「知能」
第4章 ニューロンの集合体としての脳
第5章 世界のシミュレーターとしての生成A
第6章 なぜ人間の脳は少ないサンプルで学習できるのか?
第7章 古典力学はまがい物?
第8章 知能研究の今後
内容説明
生成AIをめぐる混沌とした状況を物理学者が鮮やかに読み解く。
目次
第0章 生成AI狂騒曲
第1章 過去の知能研究
第2章 深層学習から生成AIへ
第3章 脳の機能としての「知能」
第4章 ニューロンの集合体としての脳
第5章 世界のシミュレーターとしての生成AI
第6章 なぜ人間の脳は少ないサンプルで学習できるのか?
第7章 古典力学はまがい物?
第8章 知能研究の今後
第9章 非線形非平衡多自由度系と生成AI
第10章 余談:ロボットとAI
著者等紹介
田口善弘[タグチヨシヒロ]
1961年、東京都生まれ。中央大学理工学部教授。1995年に刊行した『砂時計の七不思議―粉粒体の動力学』(中公新書)で第一二回(1996年)講談社科学出版賞受賞。その後、機械学習などを応用したバイオインフォマティクスの研究を行う。スタンフォード大学とエルゼビア社による「世界で最も影響力のある研究者トップ2%」に2021年から2024年まで四年連続で選ばれた(分野はバイオインフォマティクス)。最近はテンソル分解の研究に嵌まっており、その成果を2024年9月にシュプリンガー社から英語の専門書(単著)として出版した(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
- 評価
-





Hr本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ねこ
うえぽん
TG
りょうみや
鈴木拓
-

- 洋書電子書籍
- Selected Proceeding…