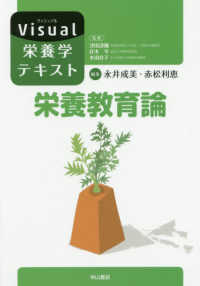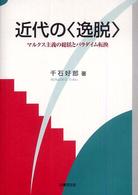出版社内容情報
日本経済が長期低迷し、「失われた30年」といわれていた2024年3月、それまで徐々に上昇していた株価が急上昇し、日経平均株価が一気に4万円を超えるという歴史的株高を記録した。自信をなくし長期低迷していた日本経済が再び息を吹き返しそうに思えるが、しかしながら、あのバブル経済がもたらした社会の実態を振り返ることなく、再びあのバブル経済のような経済発展を始めようというのだろうか?――ひたすら「経済的な豊かさ」を追求してきた日本の社会は、人間関係は希薄で無縁社会と評され、子供たちのはしゃぐ声は大人社会に迷惑がられ、幼稚園建設は近隣住民の反対運動を受ける。少子化の中で貴重な若者たちが生きる意欲を失って自殺するだけでなく、生きていても経済競争社会のストレスに耐え切れず、自宅にこもるニートといわれる者がいる一方で、精神障害で凶悪事件を引き起こす者も多い。かつては「和魂漢才」「和魂洋才」といわれた日本近代化の歴史があるが、戦後の貧しさからの脱出を達成して以降も、ただひたすら経済発展という物質文明を追及する日本社会は、「無魂米才」ともいえるありさまである。
日本人として自立の意思も志もなく、世界に誇れる伝統的な日本文化を失い、日本人の日本知らず。日本社会は今、教育現場も政治の世界も、欧米型人権主義、金銭最優先の物質文明など、欧米の価値観に毒されてしまっている。これは明らかに日本人の民度の低下であり、教育も政治も民度以上にはよくならないのではないだろうか?
本書では、そのような日本社会の行く末を憂い、日本社会と経済を真に回復させるために日本人の民度を向上させるカギとして、「企業=最強の社会人教育機関」の意義について述べる。もし民度を向上させる方法があるとしたら、それは教育であるが、その教育を左右するのは政治であり、その政治を支えるのは国民、つまり社会人である。その社会人の質を左右するのは、企業ではないだろうか? 企業はその組織活動を通じて社員、つまり国民に絶大な影響を与えている。日本社会、そして日本人が日本の伝統文化に無関心になり、ひたすら金銭を追い求めるようになったのも、日本的経営を放棄してただひたすら経済的成果を追求するアメリカ型経営、無魂米才の典型である企業の責任ではないだろうか?
「無魂米才」「無魂洋才」ではない、伝統的な日本の文化を背景にした新たな日本的企業経営の創造に取り組むための、中小企業経営者必読の経営論。
内容説明
バブル経済の崩壊は、経済的な豊かさを追求するあまり、「無魂米才」に陥った日本に対する「天の声」である―。教育現場も政治の世界も、欧米型人権主義、金銭最優先の物質文明など、欧米の価値観に毒されてしまい、民度が低下した日本人。民度を向上させる唯一の方法は、企業が変わることである。なぜなら企業は、「最強の社会人教育機関」なのだから。バブル経済崩壊という天の声を真摯に受け止め、企業はその役割を再認識し、これまでの単なる経済発展一辺倒の後を振り返り、日本社会の実態と世界の状況に目を向け、新たな時代の要求にマッチした日本的企業経営に取り組むべきではないだろうか?
目次
第1章 「バブル経済」と評されたあの経済発展は、日本社会に何をもたらしたのか(長期低迷に陥った日本の現状;「豊かさ」に慣れてしまった日本人 ほか)
第2章 民度の低下と教育の問題(次代を担う若者たちの最多死因が自殺であるという実態;危機的少子化の進行 ほか)
第3章 企業が変われば社会が変わる(「資本主義のための人間」から、「人間のための資本主義」へ;経済規模の世界ランク追求ではなく、国家の発展と国民の幸せを目指す ほか)
第4章 「いつ倒産してもいい経営」―日本コンピュータ開発の挑戦(非常識経営への挑戦とその背景;「当社の常識は一般企業の非常識」と公言する経営の実際 ほか)
著者等紹介
〓〓拓士[タカセタクオ]
1939年、大分県生まれ。1958年、大分工業高校卒業と同時に日立製作所戸塚工場入社。1960年、開校した全寮制日立工業専門学院第一期生として電子工学科入学で大学教育、続く研究科進学で東京大学工学部研究生として猪瀬博教授に師事。研究科修了と同時に元の職場に復帰、コンピュータ開発設計に従事。1972年、ドルショック不況の中、取引先ハイテク中小企業からの経営支援要請に応えて出向、翌年取締役就任と同時に日立製作所を退社。1979年、経営立ち直りと同時に起業のため単身渡米。1987年、株式会社日本コンピュータ開発の経営を引き継ぎ、独自経営理念に基づく会社に育成。2006年に自ら社長を退任、相談役最高顧問として現在に至る。社会貢献活動の一環として、主として若者の教育支援や刺激を目的とした講演活動、地方社会活性化支援、障がい者施設支援や都立特別支援学校アドバイサーなど雇用促進に重点的に取り組んでいる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
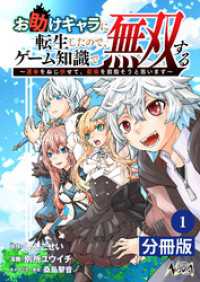
- 電子書籍
- お助けキャラに転生したので、ゲーム知識…
-
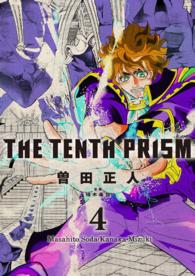
- 電子書籍
- The Tenth Prism 4