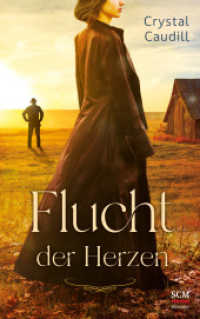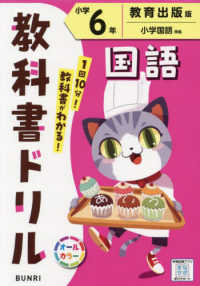出版社内容情報
●えんぴつはフランスの皇帝ナポレオンの「ムチャぶり」から生まれた?
●ミイラを巻いていた包帯を紙の代わりに使っていた時代がある?
●かつての日本には「そろばん」と「電卓」が合体したナゾの機械があった!
●修正液が生まれたのは、とある「ざんねんなタイピスト」がきっかけ?
●キミが「ガムテープ」という名前で想像しているのは、じつはガムテープじゃない?
●昔のインクはすごい酸性で、紙もインクもすぐボロボロになった?
●ボールペンを買うとき、「日本人だけがやること」がある!
●鉛筆削りが普及したのは、とある「悲しい事件」がきっかけだった?
あなたが普段つかっている、えんぴつやノートなどの文房具。
いまではいろいろ便利な機能がついているのも多いですが、じつは歴史を紐解くと「ウソでしょ!?」「なんでそうなった?」と思わずツッコミたくなる「ざんねん」なものや、いま見ても「すごい!」と驚くような「びっくり」なものまでいろいろあります。
「ざんねん」な理由も、「びっくり」な理由も、この本を読めばすべて納得!
友だちに話したくなる情報たっぷり。
子どもから大人までみんなで楽しめる文房具のひみつが大集合!
内容説明
私たちの身のまわりにあるモノはみんなどこかのだれかががんばって考えて作ったのだ。それってなんか、すごくない?「そうだったんだ!」と驚くひみつ63連発!
目次
第1章 書く、消す(今の鉛筆はナポレオンのムチャぶりから生まれた;「財閥じゃないよ鉛筆」を三菱鉛筆が作った悲しいワケ ほか)
第2章 削る、切る(鉛筆削りの普及のウラには悲しい事件があった;最初のカッターの刃は58度という中途半端な角度 ほか)
第3章 つける、貼る(舌切りすずめが食べてたのりはほぼ、ただのおかゆ;のりはもともとすぐ腐っちゃうものだった ほか)
第4章 束ねる、とめる(羊皮紙はヒツジ1頭からA4用紙4枚しか作れない;くさび形文字が直線なのは曲線が書きにくかったから ほか)
第5章 数える、刷る、入れる(かつてそろばんつき電卓という謎の合体アイテムがあった;中国と日本のそろばんは珠の数がちがう ほか)
著者等紹介
ヨシムラマリ[ヨシムラマリ]
ライター/イラストレーター。1983年生まれ。神奈川県横浜市出身。子どもの頃から絵を描くのが好きで、身近な画材である紙やペンをきっかけに文房具にハマる。主な守備範囲はノートとペンと事務用品。文具・オフィス用品メーカー大手の元社員で、現在は脱サラしてフリーランスとして活動中
高畑正幸[タカバタケマサユキ]
文房具デザイナー・研究評論家。1974年香川県丸亀市生まれ。千葉大学工学部機械工学科卒業、同自然科学研究科(デザイン心理学研究室)博士課程前期修了。テレビ東京の人気番組「TVチャンピオン」の「全国文房具通選手権」で3連続優勝し「文具王」と呼ばれる。サンスター文具にて13年の商品企画・マーケターを経て独立。文房具のデザイン、執筆・講演・各種メディアでの文房具解説のほか、トークイベントやYouTube等で人気(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
もちこ
Yuuki.
mame
Eri
Tomonori Yonezawa
-

- 和書
- 感情障害 - 基礎と臨床