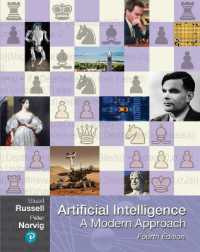出版社内容情報
経済発展と民主化を達成し、ますます存在感を高めている「台湾」は、どんな歴史を歩み、どこへ向かうのか。2024年1月の総統選挙を控えて、その歴史と現在を知る文庫版。
その歴史は「海のアジア」と「陸のアジア」がせめぎ合う「気圧の谷間」が、台湾という場所を行ったり来たりした歴史だった。その動きから生じる政治・経済の国際的な激動の中で、多様な人々が織りなしてきた「複雑で濃密な歴史」を見つめることなしに、現在の台湾を理解することはできない。
はるか以前から、さまざまな原住民族(先住民族)が生きていた台湾島が、決定的な転機を迎えたのは17世紀のことだった。オランダ東インド会社が初めて「国家」といえる統治機構をこの島に持ち込んだのである。短いオランダ統治の後、明朝の遺臣・鄭成功ら漢族軍人の時代を経て、清朝による統治は200年に及ぶが、1895年、日清戦争に勝利した日本の植民地支配が始まる。そして1945年に始まった中華民国による統治は、当時の民衆に「犬が去って、豚が来た」と言われるものだった。その中で、本省人・外省人の区別を超えて「台湾人」のアイデンティが育まれ、1990年、直接選挙による第1回総統選で「初の台湾人総統」李登輝が登場する。
『台湾――変容し躊躇するアイデンティティ』(2001年、ちくま新書)を、大幅増補して改題し、文庫化。
目次
はじめに――芝山巖の光景
第一章 「海のアジア」と「陸のアジア」を往還する島――東アジア史の「気圧の谷」と台湾
第二章 「海のアジア」への再編入――清末開港と日本の植民地統治
第三章 「中華民国」がやって来た――二・二八事件と中国内戦
第四章 「中華民国」の台湾定着――東西冷戦下の安定と発展
第五章 「変に処して驚かず」――「中華民国」の対外危機と台湾社会の自己主張
第六章 李登輝の登場と「憲政改革」
第七章 台湾ナショナリズムとエスノポリティクス
第八章 中華人民共和国と台湾――結びつく経済、離れる心?
第九章 「中華民国第二共和制」の出発
結び
補説1 総統選挙が刻む台湾の四半世紀――なおも変容し躊躇するアイデンティティ
補説2 「台湾は何処にあるか」と「台湾は何であるか」
学術文庫版あとがき
参考文献
台湾史略年表
索引
内容説明
はるか昔から多様な原住民族が生きてきた島は、一七世紀に大きな転機を迎えた。オランダ東インド会社と鄭成功の抗争、清朝の二百年に及ぶ統治と、日本の植民地支配。そしてやって来た蒋介石の中華民国。多重族群社会で「台湾人」のアイデンティティは育まれた。特異な「非承認国家」にして、奇跡の経済発展と民主化を遂げた台湾は、どこへ向かうのか。
目次
第1章 「海のアジア」と「陸のアジア」を往還する島―東アジア史の「気圧の谷」と台湾
第2章 「海のアジア」への再編入―清末開港と日本の植民地統治
第3章 「中華民国」がやって来た―二・二八事件と中国内戦
第4章 「中華民国」の台湾定着―東西冷戦下の安定と発展
第5章 「変に処して驚かず」―「中華民国」の対外危機と台湾社会の自己主張
第6章 李登輝の登場と「憲政改革」
第7章 台湾ナショナリズムとエスノポリティクス
第8章 中華人民共和国と台湾―結びつく経済、離れる心?
第9章 「中華民国第二共和制」の出発
補説1 総統選挙が刻む台湾の四半世紀―なおも変容し躊躇するアイデンティティ
補説2 「台湾は何処にあるか」と「台湾は何であるか」
著者等紹介
若林正丈[ワカバヤシマサヒロ]
1949年、長野県生まれ。東京大学教養学部卒業。東京大学大学院総合文化研究科教授、早稲田大学政治経済学術院教授等を経て、早稲田大学名誉教授。主な著書に『蒋経国と李登輝―「大陸国家」からの離陸?』(サントリー学芸賞)、『台湾の政治―中華民国台湾化の戦後史』(アジア・太平洋賞、樫山純三賞)、ほか(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。