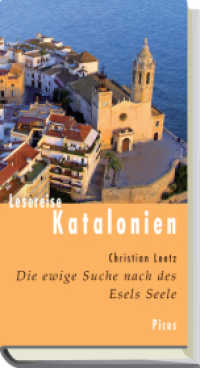出版社内容情報
家康は戦下手の俗説を正す
家康(当時松平元信)の初陣となった織田方の寺部城攻め(1558年)から、天下取りの戦いでもあった関ヶ原の戦い(1600年)と大坂の陣(1614・1615年)まで、家康は50年以上の長きにわたって戦い続けた。実は家康の合戦のほとんどは義元、信長、秀吉に動員されたもので、家康が主体的に戦った合戦は関ヶ原と大坂の陣の二つに過ぎない。また、数々のマイナスの逸話や伝承から、武将としての家康には「戦下手」というイメージがつきまとっている。本書は桶狭間の戦いから最晩年の大坂の陣に至るまで、11の主要な合戦を一次史料に留意しながら取り上げ、決して臆病者でも戦下手でもなかった武将・家康の実像を浮かび上がらせる。
*本書目次より抜粋
はじめに
徳川氏略系図
第一章 桶狭間の戦い 渡邊大門
第二章 三河一向一揆 安藤弥
第三章 姉川の戦い 太田浩司
第四章 三方原の戦い 柴裕之
第五章 長篠の戦い 光成準治
第六章 高天神城の戦い 千葉篤志
第七章 武田氏旧領争奪戦 秦野裕介
第八章 小牧・長久手の戦い 片山正彦
第九章 小田原合戦 梯弘人
第十章 関ヶ原の戦い 水野伍貴
第十一章 大坂冬の陣・夏の陣 長屋隆幸
徳川家康略年譜
おわりに
内容説明
家康(当時松平元信)の初陣となった織田方の寺部城攻め(1558年)から、天下取りの戦いでもあった関ヶ原の戦い(1600年)と大坂の陣(1614・1615年)まで、家康は50年以上の長きにわたって戦い続けた。実は家康の合戦のほとんどは義元、信長、秀吉に動員されたもので、家康が主体的に戦った合戦は関ヶ原と大坂の陣の二つに過ぎない。また、数々のマイナスの逸話や伝承から、武将としての家康には「戦下手」というイメージがつきまとっている。本書は桶狭間の戦いから最晩年の大坂の陣に至るまで、11の主要な合戦を一次史料に留意しながら取り上げ、決して臆病者でも戦下手でもなかった武将・家康の実像を浮かび上がらせる。
目次
第1章 桶狭間の戦い
第2章 三河一向一揆
第3章 姉川の戦い
第4章 三方原の戦い
第5章 長篠の戦い
第6章 高天神城の戦い
第7章 武田氏旧領争奪戦
第8章 小牧・長久手の戦い
第9章 小田原合戦
第10章 関ヶ原の戦い
第11章 大坂冬の陣・夏の陣
著者等紹介
渡邊大門[ワタナベダイモン]
歴史学者。1967年生まれ。1990年、関西学院大学文学部卒業。2008年、佛教大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。現在、株式会社歴史と文化の研究所代表取締役(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
coolflat
-

- 電子書籍
- 眠れなくなるほど面白い 図解 昭和の話
-

- 電子書籍
- 阿寒湖わらべ唄殺人事件