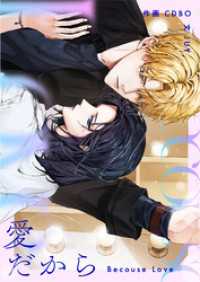出版社内容情報
「まことに、〈われ〉は、〈なんじ〉と出会うことによってはじめて、真の〈われ〉になるのである。わたしが〈われ〉となるにしたがって、わたしは相手を〈なんじ〉と呼びかけることができるようになるのである」。
「すべての真実なる生とは、まさに出会いである」。
オーストリア生まれのユダヤ人哲学者マルティン・ブーバー(1878-1965年)は、ウィーン大学で哲学や美術史を学んだのち、神秘主義的なユダヤ教の一派であるハシディズムに傾倒しつつ、ユダヤ人のパレスチナ復帰を目指すシオニズム運動に参加する。1916年にはドイツ語圏ユダヤ人の指導的機関誌となる『ユダヤ人』を創刊してその編集にあたり、またフランツ・ローゼンツヴァイク(1886-1929年)とともにヘブライ語聖書(旧約聖書)のドイツ語訳を行う。その後フランクフルト大学で教鞭をとるも、1938年にドイツを脱してイスラエルに移住。以後はヘブライ大学に勤め、エルサレムで人生を終えている。
第一次世界大戦に志願兵として参加し、塹壕のなかで着想を得て執筆されたローゼンツヴァイクの『救済の星』(1921年)の刊行後ほどなく、本書は敗戦の爪痕も未だ深いドイツで1923年に刊行された。
ブーバーの主著でもあるこの本は、「ひとは世界にたいして二つのことなった態度をとる。それにもとづいて世界は二つとなる」という一文で始まる。二つの世界のうち、一つは〈われ〉‐〈なんじ〉の世界であり、もう一つが〈われ〉‐〈それ〉の世界である。世界は、単に人間の経験の対象となるときには〈われ〉‐〈それ〉という根源語に属し、これに反して関係の世界は、もうひとつの根源語、〈われ〉‐〈なんじ〉によって作り出されるという。
「対話の思想家」と称されるブーバーは、さらに「はじめに関係あり」と語る。「私」ではなく「あなた」でもなく、〈われ〉と〈なんじ〉、そして〈われ〉と〈それ〉の出会いから始まる世界とは、どのようなものなのか。そしてそれは私たちの生に何をもたらし、どのように変えていくのか。ユダヤ思想のエッセンスに満ちた普遍的名著が、いま〈あなた〉に語りかける!
(原本:『孤独と愛――我と汝の問題』創文社、一九五八年)
【目 次】
第一篇 根源語
第二篇 人間の世界
第三篇 永遠の〈なんじ〉
資料 あとがき〔一九六二年〕(佐藤貴史訳)
訳者解説
学術文庫版解説(佐藤貴史)
内容説明
第一次大戦の爪痕も深いドイツで刊行された本書は“われ”‐“それ”と“われ”‐“なんじ”という、二つの世界があることを説く。経験と利用に覆われた“それ”の世界の軛から解放されるには、全身全霊をかけて相対する“なんじ”と出会わねばならない。その時、わたしは初めて真の“われ”となる―。対話の思想家が遺した普遍的名著!
目次
第1篇 根源語
第2篇 人間の世界
第3篇 永遠の“なんじ”
資料 あとがき(一九六二年)
著者等紹介
ブーバー,マルティン[ブーバー,マルティン] [Buber,Martin]
1878‐1965年。オーストリア生まれのユダヤ人思想家
野口啓祐[ノグチケイスケ]
1913‐75年。早稲田大学卒業。上智大学外国語学部教授を務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
金吾
iwtn_
ゆうきなかもと
オフィス助け舟
Kooheysan